�~�[�e�B���O�ɂ����钾�قƏ��̋@�\�ɂ��Ă̑Θb����
950047 ���c�_��
950050 ���،b��
��1�́@���_�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���c�_��
1. �T�v
1990�N��ɓ���A��Ƃ̎����I�����D�ʂ̌���Ƃ��ẮA�m���ɂ��Ă̊S�����܂��Ă���B�����Ă������N�A�ǂ̂悤�ɒm�����n������邩�Ƃ����v���Z�X�ɁA���ڂ��W�܂�悤�ɂȂ��Ă���B���̒m�����n�������v���Z�X�ł́A�l�Ɛl�Ƃ̑Θb���d�������B��̓I�ɂ́A�~�[�e�B���O�̂悤�ȕ����l�ɂ���b�Ȃǂ��l������B�������A�ǂ̂悤�ȃ~�[�e�B���O���A�m����n�����₷���̂��́A���ؓI�ɖ��炩�ɂȂ��Ă��Ȃ��_�������B�����ʼn�X�́A�T���I�������s�����߂ɂ���~�[�e�B���O��^�������B�����Ă��̘^�����ꂽ�~�[�e�B���O�̒��ɁA���ƒ��ق��p�ɂɌ���邱�Ƃɉ�X�͒��ڂ��A���ƒ��ق��~�[�e�B���O�ɂ����ĉ�������̖����A�@�\������ƍl�����B�����Ă����𖾂炩�ɂ��邽�߂ɏ��ƒ��ق̐��ʉ����s�����B����ɐ��ʉ��������ƒ��قɓ��v�I���������������ʁA���ƒ��قɎ����������邱�Ƃ������A�Ȃ����̎��������N���邩�ɂ��Ă̌�����T��A��4�͂ɂĉ����𗧂Ă邱�Ƃ����݂��B
�Q.�͂��߂�
�@��Ƃ����L����ł����l���鎑�Y�́A�m���ł���Ƃ̔F�����w�E�A���ƊE���킸�L�����Ă���B���̂��ߊ�Ƃ̎����I�����D�ʂ̌���Ƃ��Ă̒m���n���ɂ��ĊS�����܂��Ă���B����ɑg�D�ɂ����Ēm�����A�ǂ̂悤�ɑn������邩�𖾂炩�ɂ��邽�߂ɁA�������N�Œm����n������v���Z�X�ɒ��ڂ��W�܂�悤�ɂȂ��Ă����B�쒆�̑g�D�I�m���n�����_(1995)�ɂ��A�m���̑n�����N����v���Z�X�ɂ́A�������A�\�o���A�A�����A���ʉ��̎l�̃��[�h������A�����l�̃X�p�C�����Œm���n���������I�ɋN����Ƃ����B
���̖쒆�̑g�D�I�m���n�����_�ł́A���������g�D�I�m���n���̔��[�Ƃ��Ĉʒu�Â����Ă���B�������Ƃ́A�O���[�v���x���ł̔Z���ȑΘb��ʂ��ăO���[�v�̃����o�[�������Ă���m�������L���A�m����n������ߒ��������B�܂��������́A�m�����g�g�D�I�h�ɑn�������ŏd�v�Ȗ������ʂ����B�����̓��{�̊�Ƃł́A���̏d�v���������F�����Ă���B�����ău���[���X�g�[�~���O�A���C�K��[1]���̃~�[�e�B���O��@��p���ď]�ƈ��Ԃ̒m���̋��L�A�n����ϋɓI�ɍs���Ă����B�ŋ߂ł́A���������w��[2]�x�ƌĂ��T�O����V���������悤�Ƃ��铮��������B�@
���̂悤�ɁA�m���̋��L�A�n���ɂ��Ă̊S�́A�܂��܂����܂��Ă���B����������炪��̓I�Ɍ����ƍl������~�[�e�B���O�ɂ����āA�ǂ̂悤�ȃ~�[�e�B���O���m���̋��L�A�n���𑣐i���邩�ɂ��Ă̌����͏��Ȃ��B��X�́A�����̖��ӎ��ɗ��r������ŁA����~�[�e�B���O�̒T���I�������s�����B�����́A����O���[�v�̃~�[�e�B���O�̗l�q���u�s�q����тc�`�s�Ř^���E�^�悵�����Ƃɂ��B
�����Ŗ{�e�̒����ΏۂƂȂ��Ă���~�[�e�B���O�́A�m���Ȋw�����Ȃ̍u�`�Ȗڂ̂ЂƂł���A�m���Љ�_�̃O���[�v���[�N�ł���B�m���Љ�_�ł́A��u����w�����������̃O���[�v�ɕ����A������ꂽ�e�O���[�v���[�N�ɑ��ăr�W�l�X�v�����̍쐬���ۂ��A���̃r�W�l�X�v�����̗D������킹��Ƃ����`�Ŏ��Ƃ��s����B���̒����̑ΏۂƂȂ����~�[�e�B���O�́A�r�W�l�X�v�����̔��\�O���ɍs��ꂽ���̂ł���A�~�[�e�B���O�Řb����������e�́A��Ƀr�W�l�X�v�����̍ŏI�I�Ȃ܂Ƃ߁A�r�W�l�X�v�����\����v���[���e�[�V�����̑ł����킹�Ȃǂ����S�ł���B
�@�~�[�e�B���O�͂�����l�ɕK�v�ł���B�����Ă�������Ƃ����~�[�e�B���O���^�c���邽�߂ɂ́A�~�[�e�B���O�̉^�c�̐v�Ă��\�z���A����ɊS�̂��郁���o�[���W�߁A�I�����Ԃ����Ƃ�������{�K����O�����Č��߂āA���F���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�����ōs��ꂽ�~�[�e�B���O�́A���܂�`���I�Ȃ��̂ł͂Ȃ����߁A�~�[�e�B���O�ɎQ�����Ă��郁���o�[�ɑ��锭���̐���x�͔����B�������A�~�[�e�B���O���^�c�̊�{�����ł���A��ŏq�ׂ��_�ɂ��ẮA�[���ɒ��ӂ��Ȃ���~�[�e�B���O��i�߂��B�~�[�e�B���O�̉^�c�ړI�́A���łɏq�ׂ��Ƃ���A�r�W�l�X�v�����̍ŏI�I�Ȃ܂Ƃ߂ƁA�v���[���e�[�V�����̑ł����킹�ł���B�����o�[�͎��Ƃ𗚏C���Ă��郁���o�[�ł���̂ŁA���R���������̐��тɊւ�邱�̃v���[���e�[�V�����ɂ͊S�������Ă���B�����āA���Ԃ�2���Ԃƌ��߂Ă����B
���̂悤�ȏ������ŋL�^�����~�[�e�B���O��U��Ԃ��Ă݂�ƁA�`���I�ȃ~�[�e�B���O�ł݂͂��Ȃ����ƒ��ق���������ꂽ�B�䂦�ɖ{���͂ł̓~�[�e�B���O�ɂ����ď��ƒ��ق����炩�̋@�\�A�����Ƃ��������̂�����̂ł͂Ȃ����Ƃ����^������悤�ɂȂ����B�����ŁA����ɏ��ƒ��قɏœ_�ĂāA���͂��������ʁA�~�[�e�B���O���̉�b�̒��ŁA���ƒ��ق�������̕p�x�ŁA���݂Ɍ����Ƃ����A���֊W������ƍl����Ɏ������B���̗��R�́A���A���قƂ��ɁA��b�{�̂̒��ł̓A�N�Z���g�I�Ȗ�����S���Ă���A��b�S�̂ŁA������̒o�ɂ��K�v�ȏꍇ�ɐ����邩��ł���B�������ԉ�b������ƁA�S�̗̂��ꂪ���ɋْ����������ƂȂ�A�l�Ԃ����_�I�ɓK�x�ȊJ���������߂�Ɛ��������B
�{�e�́A��2�͂ŏ��ɂ��āA��3�͂ł͒��قɂ��ďq�ׂĂ���B�����āA��4�͂ł͏��ƒ��ق̑��֊W���L�����B�Ȃ��A���_����сA���Ɋւ��镶�������A���́A�l�@�͓��c���A���ق���сA����͍����S�����A���ƒ��ق̑��֊W�͗��҂��S�������B
��2�́@���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���c�_��
1.��s����
���́A�M���V������Ƀv���g�������ɂ��Ă̍l�@���n�߂Ĉȗ��A�����̓N�w�ҁA�S���w�ғ��ɂ���ċc�_����Ă����B���ɂ��Ă̌����͂����ɓ�̗���ɕ����邱�Ƃ��ł���B��́A�Ȃ��l�Ԃ͏��̂��Ƃ������Ƃ��Ђ�����T�����闬��ł���B�Ñ�M���V���ł́A�v���g���A�A���X�g�e���X�𒆐S�ɂ��Ă����ɏ��̈����ɂ��Ę_�����A17���I�z�b�u�Y�̍��ɂȂ�ƁA���̌����ɂ��Ă̍l�@�������[3]�A�����19�A20���I�ɓ���ƁA���̌������Љ�Ƃ����g�g�݂���l������悤�ɂȂ���[4]�B�����Ă������\�N�ł́A����I�ɔc�����悤�Ǝ��݂�ꂽ�B�����G�[��(1983)�ɂ��ƁA���ɂ͓`���I�ɗD�z�̗��_�A�Y���̗��_�A���o�̗��_������A�������w�����ȐS���I�]�ʁx�Ƃ����T�O���瓝��I�ɔc���ł���Ƃ����B����ɏ��̌��ۂ��̂��̂��R���s���[�^�[�H�w�̒m���𗘗p���āA��̋ؓ��̓����𐔗ʉ�������I�ɔc�����悤�Ƃ��铮����������B[5]���������݂Ɏ���܂ŏ��Ƃ͉����Ƃ����{���I�Ȗ₢�ɑ��Ė��m�ȓ������o���Ă��Ȃ��B
�@������̗���́A���̖{�������ł��邩���𖾂��邱�ƂɎ���u���������̉ʂ����@�\�A���\�Ƃ����������I���ʂ�����ɃA�v���[�`���悤�Ƃ��闬��ł���B��w�̕���ł́A1960�N��ɏ����P���a�ɑ��āA�D�e����^����Ƃ������Ƃ��A�Љ��Ĉȗ�[6]�A����A�S�؍[�ǁA�P���a���ɂ��D�e�����y�ڂ��Ă��邱�Ƃ�����Ă���B����̕���ɂ����ẮA���̈�̌`�Ԃƍl�����Ă��郆�[���A����葽���p����l�Ƒn���I�v�l�̊Ԃɂ͐��̑��֊W������A����͓��v�I�ɗL�ӂł���Ƃ̌������ʂ�����[7]�B����Ƀr�W�l�X�̕���ł������]�ƈ��̃p�t�H�[�}���X�ɍD�e����^���Ă���Ƃ̕�����[8]�B
���̂悤�ȏ��̌����Ɋւ���l�X�ȓ����̒��ŁA�l�Ɛl�Ƃ̑Θb�̂Ȃ��ŏ����ǂ̂悤�ȉe����Θb�ɉʂ����Ă��邩�ɂ��Ă̌������S��������n�߂Ă���B���́A�l�ԊW���~���Ȃ��̂ɂ��A���ǂ��M���W��z����ŕs���Ȃ��̂ł���Ƃ̔F���́A�����̏��ɂ��Ă̌���������҂����L������̂ł���B�ꌩ���Ƃ͖��W�Ǝv���錵�����r�W�l�X�̕���ɂ����Ă����̏d�v���ɕς��͂Ȃ��B�ߔN��Ƃ̊ԂŁA�����I�ȋ����D�ʂ̌���́A�g�D�I�Ȓm���n���ɂ���Ƃ̔F�����L�܂��Ă���B���̑g�D�I�Ȓm���n���̃v���Z�X�ɂ����ẮA�����o�[�ԓ��m�̔Z���ȑΘb���d�v�Ȗ������ʂ����ƍl�����Ă���B���������ƁA�f�B�X�J�b�V�����Ȃǂ������ɍs����~�[�e�B���O�A��c�����l������B�����̃~�[�e�B���O���c���A�����l���W�܂��čs����Θb�ɂ����āA�f�B�X�J�b�V�����������A�L�v�Ȃ��̂ɂ��邽�߂̑O������Ƃ��ă����o�[�Ԃ̐M���W�̍\�z�͌������Ȃ��B�����~�[�e�B���O���c�ɎQ�����郁���o�[�̂��݂��̋����M���W���Ȃ���A���݂��ɗ����Ȉӌ������킷���Ƃ��ł����~�[�e�B���O���c�̐��Y���ᒲ�Ȃ��̂ƂȂ邾�낤�B���́A�f�B�X�J�b�V�����ɂ����ďd�v���ƍl������M���W���\�z���邽�߂ɏd�v�Ȗ������ʂ����ƍl������B
�@�����ŁA�^�����ꂽ�~�[�e�B���O�̃e�[�v�����Ƃɏ��ƐM���W�̍\�z�̊֘A���𖾂炩�ɂ��邱�Ƃ����݂�B����ɏ�����b�̑��i�𑣂����ǂ����ɂ��Ă���������B
2.��@
���̐����J�E���g����ہA�B�ꂩ�����Ƃ�����Ȗ��ƂȂ����̂́A�ǂ̂悤�ȓ�������Ɣ��肷�邩�ł���B���́A��A�{�A���A�y�A�S�Ăɂ����ĕ\�o���錻�ۂł���A���ꂱ�������Ƃ����Ă��悢�قǂ̌`�Ԃ������邽�߁A���̔�������邱�Ƃ͔��ɍ���ł���B����̌����ɂ����ẮA�^�����ꂽ�e�[�v������̐����J�E���g���悤�Ƃ��鐧���A���肷���́A�S�ĉ����̎�������K�肷�邱�Ƃɂ����B���̊�Ƃ́A�u�́A�́A�́v�A�u�ЁA�ЁA�Ёv�A�u�ӁC�ӁA�Ӂv���A�����̎����ɂ����āuX���AX���AX���E�E�E�E�E�v�ƌ`���I�ɕ\���ł�����̂ł���B���̓����́A���̎����ł́A���Ɖ��Ƃ����߂��Ă��Ă������\���������Ă���A�Ӗ��̎����ł́A�������ꂽ�����̂ɑS���Ӗ����Ȃ��Ȃ����̂ł���B���̊����邱�ƂɊւ��ẮA�_�ސ��w�l���w�������w���̃R�X�����W�[�x�̂Ȃ��ɂ���@���n�O�u���E���_�̘_���v�̘_������̒m����S�ʓI�ɍ̗p�����B
����ɏ�����b�̑��i�@�\�����邩�ǂ���������ۂɁA10��13�b����20���܂ł̃T���v�����g���A�����N����O��̌��t�̌ꐔ���A���ߒP�ʂŐ������Ƃ��s�����B
3.���́A�l�@
�O�q������ɏ]���āA���̐����J�E���g�����B���̐��́A10������20���̘^���e�[�v��24�������B���ꂩ�玞�Ԃ�1�����Ƃ̊Ԋu�̊K���ɋ��A���ꂼ��̊K���ɂ��Ă͂܂�T���v���𐔂��A�}�\2�|1�̂悤�ɓx�����z�O���t�ɂ��ĕ\�������B
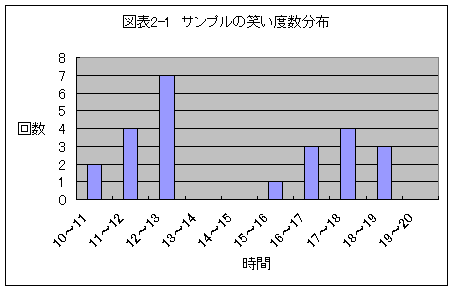 �@
�@
���̃O���t���猩�ēǂݎ��邱�Ƃ́A���̂̃T���v���ł̍ŏ��̎��ԑтɏ����p�ɂɋN���A���炭����Ə����}���ɒቺ���A�܂��~�[�e�B���O�̔��ɏ����p�ɂɋN�����ꂩ��I���Ɍ����āA�}���Ɍ������邱�Ƃł���B
���̌��ۂ���l�����鉼���Ƃ��ẮA�~�[�e�B���O���n�܂������ԑт́A�܂������o�[�Ԃْ̋��W�������A���ْ̋��W���ق������߂ɏ������p����Ă���Ƃ������Ƃł���B
����ɂ��̉������m���߂邽�߂ɘ^���e�[�v�S�̂ɂ��Ē��ׂĂ݂�B���̃e�[�v�S�̂ŏ����N�������́A�S����210��ł���B�������A���x��10���̊K������ݒ肵�ēx���̕��z���O���t�Ō���B
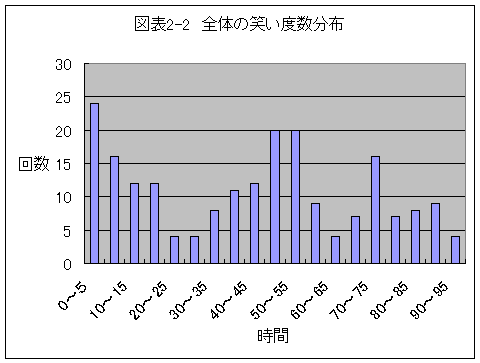
���̏�̑S�̂̓x�����z������ƁA�~�[�e�B���O�̍ŏ��̎��ԑтł́A��قǂ̃T���v���̕��z�Ɠ��l�����p�ɂɔ������Ă���A�����o�[�Ԃْ̋��������ق������Ƃ��邱�Ƃ��ǂݎ���B�䂦�ɐ�قǗ��Ă������͂�����x���ł����Ƃ�����B�����������œ�̖��_�������яオ��B��́A�T���v�����z���S�̂̕��z���n�߂̎��ԑтɏ����p��������ŁA�ꎞ���̕p�x���������A���Ոȍ~������̕p�x�������邱�ƁA��ڂ́A�T���v���̕��z�ƑS�̂̕��z�̊O�ς��Ȃ��߂�ƁA���ȑ����I�ȕ��z�ɂȂ��Ă��邱�Ƃł���B���̖��_�́A��l�͂̏��ƒ��ق̔�r�ƂŖ��炩�ɂ��A�����ł͑��̖��_�����l�@����B
�@����ł́A�Ȃ����ȑ����̂悤�ȕ��z������Ă����̂��낤���B�܂��A���̔������鐫�����l������B���郁���o�[����U���ނ悤�Ȍ�������ƁA���̌����Ɏh������āA���̃����o�[�����X�Ə����ĂԂ悤�Ȍ������Ƃ邱�ƂŁA���̕p�x�̏W�������N����A����炪�S�������_���ŋN����ƁA���ʓI�Ɏ��ȑ����I�ȕ��z�ɂȂ�̂ł͂Ȃ����Ƃ������Ƃł���B������l�����闝�R�Ƃ��ẮA�~�[�e�B���O�̂����鎞�ԑтł��̏u�Ԙb��ɂȂ��Ă��邱�ƂɊւ��āA��X�́A�قړ��l�̍s�����Ƃ�A����炪���̊K�w�\���ɂȂ��Ă���̂ł͂Ȃ����Ƃ������Ƃł���B�܂�A�~�[�e�B���O�S�̘̂b��Ɋւ����X�̔����A���̃~�[�e�B���O�̂��镔���ɑ����X�̔����A���̂��镔���̈ꕔ���ɂ������X�̔����Ƃ������ɂ��āA�K�w�\�����Ȃ��A�����̔��������ȑ����̑S�̑����`�����Ă���Ƃ������Ƃł���B�~�[�e�B���O�Ƃ������̂́A���̃~�[�e�B���O�̋c��ɂȂ��Ă��邱�Ƃ�����b���Ă���̂ł͂Ȃ��A���̋c��Ɋւ���ׂ��Ȃ��Ƃ������ɘb�����Ƃ��l����A�~�[�e�B���O����̊K�w�\���ɂȂ��Ă���Ƃ������Ƃ͕s���R�ł͂Ȃ��B�ȏ�̗��R����T���v���ƑS�̂̕��z�����ȑ����I�Ȍ`�Ō����ƍl����B
���ɏ�����b�̑��i��}��@�\��������B���������Ȃ�炩��b�𑣐i����@�\������Ȃ�A�����N����O�ɂ���ׂ����ꐔ�ɔ�ׂāA���̌�ɂ���ׂ������ƌꐔ�̕����������Ƃ��l������B�䂦�ɁA���̒���̌ꐔ�����O�̌ꐔ��葽���Ƃ��������𗧂ĂāA���̉�����������B
�����ŗp����T���v���́A��b�������Ƃ��e�Ǝv����10��13�b����20��00�b�ł���B���̃T���v������22��̏��̑O��̌ꐔ�����o���A�����ς��Ă݂�ƁA
|
���̒��O�̌ꐔ���ρ@15.72727 |
|
���̒���̌ꐔ���ρ@8.590909 |
�ƂȂ�A���������߂錋�ʂƑS���t�ɂȂ�B���̕��ς̍��͓��v�I�ɗL�ӂł���Ƃ̌��ʂ��o�Ă���B
���ɁA���͈͂̔͂��L���āA���̋N�������O��̌ꐔ�����łȂ��A����炪���̒��ق܂��͏����N����܂ł̌ꐔ�������邱�Ƃɂ��ĕ��͂����݂��B���������O�͋t�Z���Đ������B�ȉ��A��Ɠ����悤�ɂ���ƁA
|
���̒��O�̌ꐔ���ρ@36.4545 |
|
���̒���̌ꐔ���ρ@32.4545 |
���̏ꍇ�ɂ����Ă����̒��O�̌ꐔ�̕�������̌ꐔ��葽���B���������̍��͓��v�I�ɗL�ӂł͂Ȃ������B
����ɂ��̉����������邽�߂ɕʂ̕��@��p�����B����́A���̑O��ɂ����Ăǂꂾ���̉�b�̂��Ƃ肪���������Ƃ������Ƃł���B�Ⴆ����l������������������Ƃ肪���A�����ĒN����������������Ƃ�͓������̒��ق܂��͏����N����܂Ő�����B���O�Ɋւ��Ă͒��O�̌ꐔ�̕��ςƓ��l�t�Z���Đ�����B�����Ă��ꂼ��̏��ɂ��Ă��̍�Ƃ��s���A���ς��Ă݂�ƁA
|
���O�̂��Ƃ�̕��ρ@3.318182 |
|
����̂��Ƃ�̕��ρ@2.772727 |
�ƂȂ�A��͂艼�����x���ł��Ȃ��B
�@�Ō�ɁA���̂��Ƃ肪�ʂ����Ăǂꂭ�炢�̎��ԊԊu�Ō����̂��Ƃ������Ƃ��l�����B�����Z�����Ԃł�����Ƃ肩�玟�̂��Ƃ�Ɉڂ�A��b�������炩���i���ꂽ�ƍl���邱�Ƃ��ł���B���̉����𑪒肷�邽�߂ɁA�����N���������Ԃ��玟�̏��܂��͒��ق��N�������Ԃ̎��Ԃ����߁A���̊ԂɌ��킳�ꂽ��b�̂��Ƃ�̐�������A���̏o���l��S�đ����ĕ��ς����߂��B�����āA
|
���O�̈���Ƃ蓖����̕b�����ρ@3.286364 |
|
����̈���Ƃ蓖����̕b�����ρ@3.172727 |
�ȏ�̌��ʂ̂悤�ɂȂ�A����̐��l�Ɏ�O�����Ȃ��̂����������邪���v�I�ɂ͗L�ӂƂ͌������A���lj����������邱�Ƃ͂ł��Ȃ������B
�ȏ�̕��͂̌��ʂ��܂Ƃ߂�ƁA���̒��O�ƒ���́A������́A���O�̂ق�����b�𑽂������Ă���X�����݂���B���ɁA���̒��O����ɔ�����ꂽ�ꐔ�Ɋւ��Č����A���O�̕�������ɔ�ׂČꐔ���������v�I�ɂ��L�ӂł���B���̗��R�Ƃ��čl������̂́A���O�́A����U���Ƃ���Ӑ}���猾�t���������Ȃ�A�������̕��́A���̏���U�������ɒP���ɔ������邾���ŁA����ȏ�Ȃɂ��������Ƃ���X�������Ȃ��̂ł͂Ȃ����ƍl������B����ɍ���̌��ʂ���́A������b�ɍD�e�����y�ڂ��Ƃ�������I�؋����Ȃ������B�ނ�����̋@�\�Ƃ��ẮA�~�[�e�B���O�����悭���邽�߂̊����������i�ْ��W�̊ɘa�Ȃǁj���傫���̂ł͂Ȃ����Ǝv���B
4.�C���v���P�[�V����
����̌����ł́A���́A�Ӗ����Ȃ��Ȃ����̒f���I���������ꂽ�Ƃ��ꗥ�ɏ��ł���Ɣ��肵���B�������A���ɂ͑��푽�l�Ȏ�ނ�����̂����Ԃł���B���̏��̗l�X�Ȍ`�Ԃ���ʂ��邽�߂ɉȊw�I�ȕ��@��p���ĕ��ނ��邱�Ƃ����݂��Ă���B�������̎��݂����܂������A�����œ���ꂽ���ފ�����Ƃɂ��āA�ǂ̂悤�ȏ��̂Ƃ��ɉ�b�̊��������}���A�܂��͂��̋t������̂��A��c�̎�ނɂ���ď��ɂ��Ⴂ���o�Ă���̂��ȂǂƂ��������ƂɐV���Ȍ����̐i�W�����҂ł���B
����ɍ���̌����ł͏�����b���i�Ɍq���錈��I�ȏ؋����Ȃ��������A�����T���v���𑝂₹�A��������ʂ��邱�Ƃ��l������B
�Ō�ɂ��̘_���ŏ����Љ���w��x�ɂ��Ă��V���Ȍ����̎�����ł��邩������Ȃ��B�w��x�̗��_�̎�|�́A�l�Ԃ��A�N���ƃR�~���j�P�[�V�������s���Ƃ��A�ł����z�I�ȐS����Ԃł���ƈÖقɉ��肵�������ŁA���̗��_����}�낤�Ƃ��Ă���B�����������w�ɂ������̗��_�Ƃ͈Ⴂ�A�ώ@�ΏۂƂȂ���̂��������ۂł͂Ȃ��A�l�Ԃ̐S�����ۂȂ��ߋq�ϓI�Ȉ��ʊW�̋L�q������ł���B���́A���̍���ȗ��_�����s���\�����߂Ă���B��̓I�ɂ́A���́A��̒�`�ɂ��郁���o�[�Ԃŋ��L�����т����W���Ƃ������̂��A���ۓI�ɗ��t���Ă�����̂ł���B���������c�̃����o�[�Ԃɂ����ĉߋ��ɂ������т����W���A�����Ƃ��������̂����L���Ă��Ȃ���A���Ƃ������ۂ��N���邱�Ƃ͍l���ɂ����B�䂦�ɏ����w��x�Ƃ������ۂ��N�����Ă���w�W�Ƃ��Ďg�����ƂŁA�V���ȏ�̗��_���̎��݂͏\���Ɋ��҂ł���B
�@
��R��
���ف@
1.�T�v
�@�~�[�e�B���O�����Ă��鎞�A��������ׂ�Ȃ��Ŗق��Ă���l��ǂ���������B���w�Z�⒆�w�Z�Ƃ������A�Ⴂ�Ƃ�����b������������Ƃ��ɁA�Â��ɂ��Ă���l������B�����������b�������̏�ł̒��ق́A�����������ɓI�ł���Ɗ�������ł͂Ȃ����낤���B�����͓��퐶���̒��ŁA��b�͐�Εs���ȗv�f�ł���B
�@�L������ܔłɂ��ƁA���ق͇@���܂��āA���������Ȃ����ƁB�A���������ɐÂ��ɂ��Ă��邱�ƁB�Ƃ���B�L�����̒�`������A���ق���̓}�C�i�X�̃C���[�W��������B
�@�l�́A�ΐl�I�R�~���j�P�[�V����[9]�@�𐬗�������ŁA�������̈ӌ���C������ɓ`�����i�Ƃ��āu�b���v�s�ׂ��s���邪�A����ȊO�ł�����ɍl����`���邱�Ƃ��ł���B����́A��R�~���j�P�[�V�����ł���B��R�~���j�P�[�V�����́A�ӎ����������x���Ⴂ�̂ŁA����̓`�B�ɓK���Ă��āA����I�R�~���j�P�[�V������₤�@�\�������Ă���iArgyle,1972�j�B�܂�A��X�͒��قƂ����鉹�����Ȃ������ōs���Ă��铮��A���Ȃ킿��R�~���j�P�[�V�����͂��邱�Ƃɂ���āA���肩��̏���������x���邱�Ƃ��o����̂ł���B
�@�����[�r�A��(Mehrabian,1968)�́A���b�Z�[�W�̑S�̂̈�ۂɂ��Ď��̂悤�Ȍ����������Ă���B
���b�Z�[�W�S�̂̈�ہ�0.07�i������e�j�{0.38�i�����j�{0.55�i�\��j
���̎��ł́A�ΖʃR�~���j�P�[�V�����ɂ����ẮA������\��܂��R�~���j�P�[�V�������d�v�ł���Ƃ������Ƃ�\�����Ă���i��4�́j�B
�@���m�̂��Ƃ킴�ɁA�u���ق͋��A�Y�ق͋�v[10]�Ƃ����̂�����B���̂��Ƃ킴�́A���ق̂ق����悢�ƌ����Ă���B��g�N�w�E�v�z���T�ɂ��ƁA���قƂ͂���Ȃ錾��̌��@�Ԃł͂Ȃ��A��������������Ɋ�������ϋɓI�\��ł���B�Ə�����Ă���B����Ƀn�C�f�K�[�ɂ��A���ق͌��̈ꑶ�ݗl���Ƃ��āA�u���鎖���ɂ��đ��҂Ɍ������Ė��m�Ɏ��Ȃ�\�����邱�Ɓv�Əq�ׂĂ���B���������|���e�B�ɂ����ẮA�u�N�w�͒��قƌ��t�Ƃ̑��ݓ]���ł���v�Əq�ׂĂ���B����ɁA���t���ꎩ�̂ɂ́A�R�~���j�P�[�V�������e�̑S�e��^���͓��ڂ����ɁA���O�̐g�̓I�ȕ\���A�܂Ȃ����A������ǂ݁A�����Ē��قɏd�v�ȏ����̂��邱�Ƃ�����B
�@�ȏ�̂��Ƃ���A���ق͈ꌩ�A���ɓI�ȍs���̂悤�Ɏv���邪�A���ق̊Ԃɍs�����I�R�~���j�P�[�V�������s���Ă������A���ɓI�ł͂Ȃ��Ƃ������Ƃ�������B�ł́A���ق̏�Ԃ̎��ɁA�l�͉������Ă���̂��낤���B���������Ă݂邱�Ƃɂ���B
�E�l�̘b���Ă���B
�E�����Č��ɂ��čl���Ă���B
�E�ʂ̂��Ƃ��l���Ă���B
�E�����l���Ă��Ȃ��B
�@�l�́A�R�~���j�P�[�V�������s���Ă���Ƃ��A�������l���遨�b���Ƃ�������A�̗����g�ނ̂ŁA���ق̎��ɐl�Ԃ́A���R��L�̂悤�ȍs�����s�����Ƃ����������B�l���Ă���Ƃ��ɂ́A�l�͎����̈ӌ������Ēm���n�����s���Ă���B�����ĕ\�o�����ꂽ�m�����A����I�R�~���j�P�[�V�����𗘗p���āA�b���̂ł���B���̌��ʁA��X�͂��Ƃ킴�ɂ���悤�ɁA���قɂ͐����͂�����ƍl����B�܂��A�{���͂ł́A�l�ɂ�钾�ق̌��ʂ̑��ɁA�~�[�e�B���O�S�̂ł݂����ق̌��ʂɂ��Ē��ׂ邱�Ƃɂ����B
�@��X�́A�~�[�e�B���O�S�̂ɂ����钾�ق̌��ʂƂ́A�u��S�̂̃��Y���𐮂��@�\�������A�����ɒm���n�����s�����߂̏d�v�ȃv���Z�X�ł���v�Ƃ����������\�z�����B����ɁA�u���ٌ�̉�b�̕������͏��Ȃ��v�����āA�u���يԂ̉�b�������Ȃ��v�ƍl�����B�����ŁA��̖�肪�������B���ق̒�`���ǂ̂悤�ɍs�����B�����āA�����̏�Ԃ����b�ȏ㑱�����璾�قƂ��ăJ�E���g�����̂��Ƃ������ł���B���̉����ĂƂ��āA���ق̃f�[�^��2��ނɕ����邱�Ƃɂ����B�P�́A�����̏�Ԃ������ł��������ꍇ�ɒ��قƂ��ăJ�E���g������B�����āA����1��3�b�ȏ㖳���̏ꍇ�̒��قƂ��ăJ�E���g������ł���B���̗����̌��ʂɑ���_������ꂽ�ꍇ�A���ق̒�`�Â����s��Ȃ�������Ȃ��ƍl����B�f�[�^�̌��͈ȉ��̒ʂ�ɍs�����B
�@�ŏ��ɁA���ق̐����J�E���g�����B�J�E���g���@�́A������Ԃ������ł��������ꍇ(A)��3�b�ȏ㖳����Ԃ������ꍇ�iB�j�ł���B���ɂ��ꂼ��̏�ԂŁA���قƒ��ق̊Ԃɂ����b�̐����J�E���g�����i�}�\3�|1�j�A�i�}�\3�|3�j�B3�ԖڂɁA���ꂼ��̏�ԂŁA���ٌ�̉�b�̕������͂����i�}�\3�|2�j�A�i�}�\3�|4�j�B�ȉ������̌��ʂł���B
�@�Q.�e�f�[�^�̌���
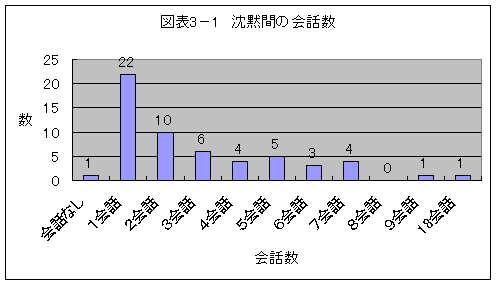
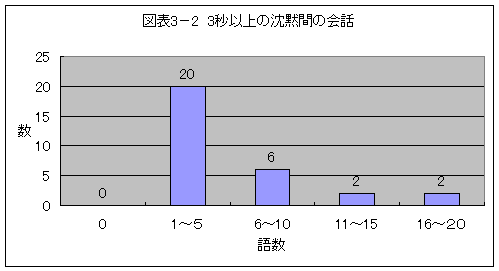
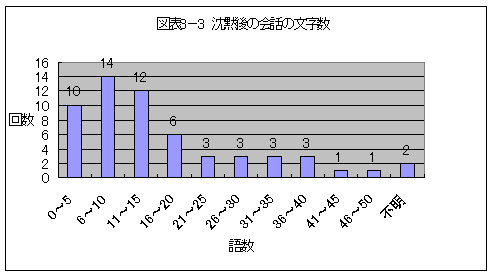
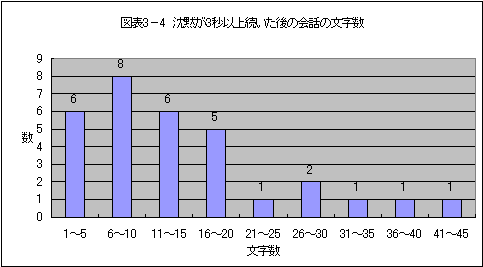
�i�P�j���ق̐�
�@�f�[�^���̒��ق̐��́AA��57�AB��31�ł���B�S�f�[�^���Ԃ�9��42�b�̊Ԃ�57�̒��ق�����̂ŕ��ς���Ƃق�10�b��1�����Ԃ����邱�ƂɂȂ�B
�i�Q�j���قƒ��ق̊Ԃɂ����b�̐�
�@�}�\3�|1�̏ꍇ�A�S56��47�P�`�T��b�����Ȃ��B�܂��A�}�\3�|3�̏ꍇ�����l�ɑS30�A20�P�`�T��b�ł���B�O�҂͑����ق�84���ŁA��҂�67%�Œ��يԂ̉�b�̐����P�`�T��b�ƂȂ��Ă���B
�i�R�j���ٌ�̉�b�̕���������
�@�}�\3�|2�̏ꍇ�O�`�T�ꐔ��10��A�U�`10�ꐔ��14��A11�`15�ꐔ��12��ƑS57�A36��15�ꐔ�ȉ��ł���B�����ł́A63���ƂȂ�B�}�\3�|4�̏ꍇ�����l��15�ꐔ�ȉ��̏ꍇ���S31��20��B������������ł͑S�̂�65����15�ꐔ�ȉ��ł���B
3.�~�[�e�B���O�ɂ����钾�ق̌���
�@�P�`�R�̌��ʂ�����ƁA������Ԃ������ł��N�������ꍇ���璾�قƂ��Č��邱�Ƃ��o����B������Ԃ̎��Ԃ̒����ɂ���ĉ�b�̌ꐔ�Ɋւ��Ă̕ω����Ȃ��������߂ɁA���قƂ������삻�̂��̂��d�v�ȈӖ������ƍl������B�܂��A���يԂ̉�b�̐������Ȃ��������A����́A�T���v���̃~�[�e�B���O���W�c�ɂ��A�C�f�B�A�����ɂ����Ƃ��K�����u���C���X�g�[�~���O�ibrainstorming�j�@[11]��p���Ă��邱�Ƃ��v���ł���B�܂�A�A�C�f�B�A���o���ړI�̂��߂ɁA�ӌ������݂Ɍ����o���Ă����A���ݓI�ȏ�ʂ������A�܂��A�����̔����̒��ɂ͂Ђ�߂�������������ł���B����ɒ��ق̊Ԃɍs���Ă����v�l�̌��ʂ𑁂�����I�R�~���j�P�[�V�����Ƃ��ĕ\�o�����邽�߂ɁA�ꌾ�ŕ\���ł���P�ꂪ�����B
�@���ق́A�ΐl�R�~���j�P�[�V�������s�����ɁA���ɓI�ȍs���ł���B�������A�~�[�e�B���O���s���ۂɁA���ق͌��ݓI�Ȉӌ��̍\�z���s����ŏd�v�Ȗ�����S���Ă���B�܂��Ɂu���ق͋��A�Y�ق͋�v�ł���B�����A�I�n���ق�ۂ��Ƃ͔����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�~�[�e�B���O�͉䖝���Ȃ̂ł͂Ȃ��A�R�~���j�P�[�V�����Ȃ̂�����B
��S�́@���ƒ��ق̑��֊W�@�@�@�@�@�@�@�@���c�_���@���،b��
���ƒ��قɂ��ẮA��Q�͂Ƒ�3�͂ł��ꂼ��q�ׂ��B���̏͂ł͏��ƒ��ق��ǂ̂悤�ɊW���Ă���̂����L���B
��3�͂ŁA����R�~���j�P�[�V�����A��R�~���j�P�[�V�����ɂ��ďq�ׂ��B�����ł́A���ƒ��قƂ�����R�~���j�P�[�V�����ɂ��đ����I�ɍl���Ă݂����B
�P,��R�~���j�P�[�V����
�@�l�Ԃ̏�ɂ́A��{���y������B�����̊���Ȃ��ɂ́A�l�ԂƂ͌�邱�Ƃ��o���Ȃ����낤���A����������������邩�炱���A�l�Ԃł���B�G�N�}���iEkman,1972�j�́A��{��Ƃ��āA�K���A�߂��݁A�{��A�����A�����A���|�̂U�������Ă���B�l�́A�ǂ̂悤�ȕ\��ifacial expressions�j���ǂ̂悤�ȏ��\�o������̂��m���Ă���B�����̎��ɂ́A��Ȃ����낤���A���Ȃ��Ƃ��������ꍇ�y�������Ƃ͂��肦�Ȃ��B���̏ꂻ�̏�̏ɉ����āA�\������B���̑��ɁA��R�~���j�P�[�V�����́u�����v�A�u�g�̓���v�A�u�p������v������[12]�B�p������iparalanguage�j�́A���b�̓��e�ȊO�̑��ʂ��w���B���̑傫���A�}�g�A���فA�����ԈႢ�Ȃǂł���B�܂���Ƃ����\��ƒ��ق̃p������͓�����R�~���j�P�[�V�����ł���A�Ƃ��ɁA��b��ł͓��l�̂͂��炫���s���Ƃ������Ƃ�������B����ł́A�~�[�e�B���O�ł͂ǂ̂悤�ȓ������s���Ă���̂��B�ȉ��̃f�[�^�Ɏ����B
2,���قƏ��̑��֊W
�@�}�\4�|1�A�}�\4�|2�A�}�\4�|3�́A���قƏ��̎��n����O���t�ɂ������̂ł���B�}�\4-1�́A���̌�ɂ����b�̐����A�}�\4-2�Ɛ}�\4-3�͒��ق̌�ɂ����b�̐����̕b���ŕ����Ă���B���Ȃ킿�A�O���t�̒l�����Ȃ��ꍇ�́A���i�������͒��فj�������ɋN����Ƃ������Ƃ�����킵�A�O���t�̒l���傫���ꍇ�́A���i�������͒��فj�����܂�N���Ă��Ȃ��Ƃ������Ƃ�\���Ă���B
�@���قƏ��̃O���t�����Ă݂�ƁA���ق������Ƃ��͏������Ȃ��A���������Ƃ��͒��ق����Ȃ����Ƃ��킩��B����������A��b�����ׂĂɂ����Ē��قƏ��Ƃ�����R�~���j�P�[�V�������s���Ă��邱�ƂɂȂ�B�܂��A���قƏ������݂ɔ������Ă���_�ɂ��ẮA�����͎v�l��l�̘b���Ƃ����l�Ԃْ̋���ԂƁA���Ƃ����o�ɏ�Ԃ����݂ɍs���A�~�[�e�B���O�S�̂̃��Y����ۂ��A�W���͂ȂǂƂ������~�[�e�B���O�ɒ������\�͂����܂��ێ�����Ƃ����l�����N���邩��ł���B
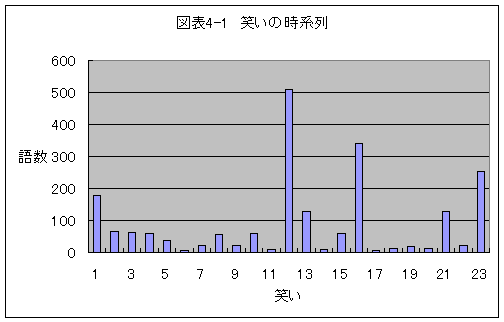
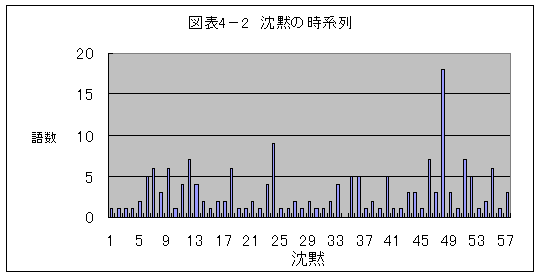
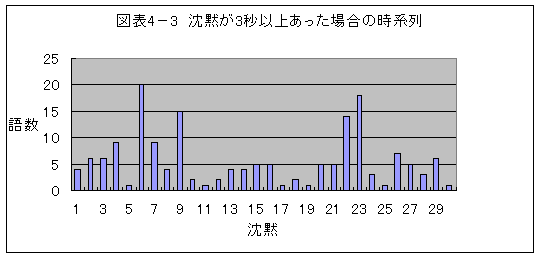
3.����̓W�]�Ɖ���
�@���̏͂ł́A���ƒ��ق̑��֊W�ׂ��B���ƒ��ق͂Ƃ��ɁA��R�~���j�P�[�V�����ł���A���قƏ��ɂ�����ْ���Ԃƒo�ɏ�Ԃɂ��A�~�[�e�B���O�S�̂̃��Y����ۂ��Ƃ��킩�����B
�@��X�͍���̓W�]�Ƃ��āA�V�����������Ă���i�}�\4�|4�j�B�쒆���̒m���ϊ����[�h�iSECI���f���j�̕\�o��(Externalization)�ƘA�����iCombination�j�ł͌���R�~���j�P�[�V�������s���Ă���A���ʉ��iInternalization�j�Ƌ������iSocialization�j�ł͔�R�~���j�P�[�V�������s���Ă���B�܂��A�m���n�����s����Ƃ��ɁA���قƏ��͒m���̏[�U���ʂ��s���Ă���B�[�U���ʂƂ́A�m���n�����s���Ă���Ƃ��A���قƏ������̃g���K�[�ƂȂ�A�\�o����A���������āA�m�����J������Ƃ������Ƃł���B���قƏ����m���n���ɑ傫���ւ���Ă���_���A����̓W�]�Ƃ���B
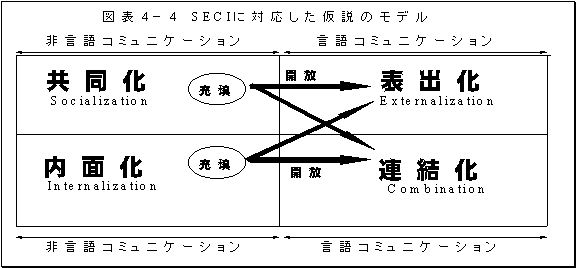
��5�́@����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���،b��
�����̓~�[�e�B���O�ɂ�����A���ƒ��قɂ��Ē������������Ă����B�~�[�e�B���O�ł͏��ƒ��ق�������x�A���݂ɏo������B�܂�A�ْ��ƒo�ɂ̑��ݍ�p���]�܂����Ƃ������_�ɂȂ����B�T���v���f�[�^�����Ƃ̈�̃~�[�e�B���O�Ƃ������Ƃ�����A������x���[�Y�ȏ�ł��������̂����A�����Ȃ�~�[�e�B���O�̏�ł����Ă��A�ΐl�R�~���j�P�[�V������}���ł́A���̂悤�ȋْ��ƒo�ɂ̕K�v����������B�������A�������̉ۑ肪�c�����B�܂����ɁA���ƒ��وȊO�̔�R�~���j�P�[�V�������A�~�[�e�B���O�łǂ̂悤�Ȍ��ʂ������炷�̂������邱�Ƃł���B���ɁA����̃T���v���ȊO�̃~�[�e�B���O�ł��A���l�̌��_���^�ł��邩�ł���B���ԓI����ۑ�ɑ��钧�킪����ȏł��������A�����̒���Ƃ��Ď���ɂȂ������ƍl����B
�{���e�������グ�邽�߂ɗl�X�Ȏh���ƗE�C��^���Ă����������{�����Ȃ̑n�����J���V�X�e���_�̓��g�w�搶�Ɋ��ӂ̈ӂ�\���A�����ɕM��u�����Ƃɂ���B
���Q�l���� �ꗗ��
Avener.Ziv. (1984)
Personality and Sense of Humor. New
york: Springer.[���ؕۍK��(1995)�w���[���A�̐S���w�x��C�ُ��X].
Bergson, H.(1975 Originay published 1899) Le rire.
Paris: PUF [�g�E�x���N�\���@�ђB�v��(1899)�w���x��g���X].
Cousins�EN�@���c�L��(1979)�w���Ǝ����́x��g���X.
D.C.Gause and
Gerald M.Weinberg.�@���c����Y�ďC�@���u�Îq��w�v���d�l�̒T���w�x�����o�Łi1993�j
�h�i���h.C.�S�[�X�@�����@�ؑ����@�w���C�g�A���Ă��܂����x�|��蔭���̐l�Ԋw�@�����o�Łi1987�j
Everett M.Rogers���@���c������w�R�~���j�P�[�V�����̉Ȋw�x1992�@�����o��
���{�ǖ��Ғ��@�w�R�~���j�P�[�V�����w�ւ̏��ҁx1997�@��C�ُ��X
���G�ق�(1997)�w���̌����x�t�H�[�E���[
�_�ސ��w�l���w������(1999)�w���̃R�X�����W�[�x�������[
Loehr�EJ�@���䂩���(1992)�w�r�W�l�X�}���̂��߂̃����^���E�^�t�l�X�xTBS��u���^�j�J
���������u�w�R�~���j�P�[�V�����̐S���w�x1999�i�J�j�V���o��
Morreall. J. (1983) Taking Laughter Seriously. New
York: State University of New York Press. [�X���L���@(1995)�w���[���A�Љ�����Ƃ߂āx�V�j��.]
Nonaka, I. and H. Takeuchi.(1995) The Knowledge-Creating Company. New York: Oxford University Press.[�~�{������(1996)�w�m���n����Ɓx���m�o�ϐV����.]
������ (1998)�w�u���v�̎����́xPHP������.
Shimizu, H.
(1994). What is �gBa�h, and the Significance of the Research of �gBa�h, Holonics, Vol.4, No.1:pp53-62.
Porter, M.E. (1980) Competitive Strategy. New York: The Free Press. [�y�E�����ݎ��E�����ƕv��(1982)�w�����̐헪�x�_�C�������h��]
���i�r�Y�@���ҁ@�w����Љ�S���w�x,������w�o�ʼn�i1998�j
�����L�v�@�ҁ@�w�g�D�����̌o�c�w�x�����o�ώҁi1997�j
Copyright © 2000 Hiroki Shimada
and Keita Takagi. All right reserved.