Japan Advanced Institute of Science and Technology. School of Knowledge Science, Umemoto Lab.
知識管理から知識経営へ
-ナレッジマネジメントの最新動向-
野中郁次郎
北陸先端科学技術大学院大学 知識科学研究科 助教授
梅 本 勝 博
1.はじめに
1990年代は、企業の競争優位の源泉としての知識への関心が、世界中で著しく高まった10年であった。アメリカのコンファレンス・ボードの調査によれば、現在、世界の多国籍大企業の80パーセントが、何らかの形でナレッジ・マネジメントのプロジェクトを実施しているそうである。
最近、ナレッジ・マネジメントは、このままでも通じるようになってきたが、日本語としては「知識管理」と「知識経営」の二つの訳が可能である。前者が、単なる既存の知識の管理を意味しているのに対して、野中・紺野 [野中99] によって人口に膾炙し始めた後者は、前者のレベルを超えて、「知識に基づく経営」、もっと正確に言えば、新しい知識を創り続けることによる経営、すなわち「知識創造の経営」 を意味している。
この後者の定義によれば、「知識管理」はナレッジ・マネジメントの第一段階にすぎない。時折マスコミでナレッジ・マネジメントを既存の知識の共有・活用と解説しているのを見かける。それだけでもできれば、誉められるべきかもしれない。しかし、既存の知識の活用だけで充分だ、と思わせるその弊害を考えれば、その解釈はまちがっていると言わざるをえない。さらに言えば、現在普及し始めている、ITを活用したナレッジ・マネジメントの実践は、その意味で「知識管理」のレベルに留まっている。
本稿の目的は、日本におけるナレッジ・マネジメントの最近の理論的展開 [梅本96, Nonaka 96, von Krogh 97, Nonaka 98, 野中99, 野村99, von Krogh 00, Nonaka 00a, Nonaka 00b, Nonaka 00c, Nonaka 00d]と実践の最新動向を、社会科学の視点からサーベイすることにより、上記のような浅薄な理解ないし誤解を減らすことである。
2.最近の日本におけるナレッジ・マネジメントの理論と実践の展開
ナレッジ・マネジメントの基礎理論としての組織的知識創造理論の最近の展開を紹介する前に、理論の要点を簡潔に説明しておきたい。まず、基本的な前提として、(1)知識には、明確な言語・数字・図表で表現された「形式知」と、はっきりと明示化されていないメンタル・モデルや体化された技能としての「暗黙知」という二つの相互補完的なタイプがある、(2)人間の創造的活動において、両者は互いに作用し合い、形式知は暗黙知へ、暗黙知は形式知へ互いに成り変わる、(3)組織の知は、異なったタイプの知識(暗黙知と形式知)そして異なった内容の知識を持った個人が相互に作用し合うことによって創られる、と考えるのである。
この前提に基づけば、我々が「知識変換」と呼ぶ四つの知識創造の様式(モード)が考えられる。すなわち、個々人の暗黙知(思い)を共通体験をつうじて互いに共感し合う「共同化 (Socialization)」、その共通の暗黙知から明示的な言葉や図で表現された形式知としてのコンセプトを創造する「表出化 (Externalization)」、既存の形式知と新しい形式知を組み合わせて体系的な形式知を創造する「連結化 (Combination)」、そしてその体系的な形式知を実際に体験することによって身に付け暗黙知として体化する「内面化 (Internalization)」である。組織の知は、この四つのモードをめぐるダイナミックなスパイラルによって創られる。この組織的知識創造のプロセス・モデルは、四つのモードのイニシャルを取って「SECIモデル」と呼ばれ、ナレッジ・マネジメントの基礎理論として、世界中で広く知られている(図1参照)。
現在、ナレッジ・マネジメントの基礎理論としての組織的知識創造理論は、4つの要素から構成されている。すなわち、(1)「SECIモデル」、(2)知識創造のための共有されたコンテクストとしての「場」(これも[Nonaka 98]によって、baとしてナレッジ・マネジメントの分野で基本的な用語として広まりつつある)、(3)知識創造プロセスにおける材料と成果としての知識資産、(4)知識創造プロセスの促進要因を提供する「ナレッジ・リーダーシップ」である。これら四つの要因が相互に作用し合うことによって、「知識経営」が可能になるのである。次節では、ナレッジ・マネジメントの基礎理論としての「組織的知識創造理論」における最近の発展として、これら四つの要素を一つずつ説明する。
実践面については、日本企業におけるナレッジ・マネジメントは、我々が日本から世界に発信した「知識創造企業The Knowledge-Creating Compnay」[Nonaka 95, 野中96]のコンセプトで知られている「組織的知識創造理論」の影響を、程度の差はあれ受けている。しかし、その四つの要素をすべて含む、あるいはそれぞれを理論どおりに実践している企業事例は見あたらない。したがって、それぞれの要素に多少の変更を加えて実践している企業事例を、各要素の説明の後で紹介する。
2.1 自己超越プロセスとしてのSECI
SECIモデルを理解する際に注意すべきポイントが二点ある。第一に、SECIで示される知識創造プロセスは、スパイラルの形を取り、単なるサイクルではない、という点である。この「知識スパイラル」において、暗黙知と形式知の相互作用は、知識変換の四つのモードをつうじて増幅されていく。それは、個人のレベルから始まり、個人、課、部、事業部、そして組織の境界を超越する相互作用共同体をつうじて広がっていくダイナミックかつ終わりのないプロセスである。それを知の視点から見れば、スパイラルが大きくなるにつれて、個人の知から、グループの知へ、そして組織の知へ(しばしば組織間の知へ)と上昇し、内面化によって再び個人の知へ戻ることになるが、そのとき個人の知の内容はずっと豊かになっているのである。
第二に、組織的知識創造は、個人が自分の新たなアイデンティティを、最初にグループの中で、次に組織の中で見つける、すなわち新たな経験と知識で豊かになった自己を発見する、自己超越プロセスであるということである(図1参照)。共同化において、個人は、徒弟制度やOJTで見られるように、同じ時間と空間の中で直接的な(すなわちリアルな)体験を共有することによってスキルを共有したり、他人の立場に身をおくことによって同じ状況をその人がどう見ているかを共感する。表出化においては、それらの互いに共感された個人のメンタル・モデル(暗黙知)は、対話によってグループのメンタル・モデルに統合され、明示的なコンセプトに表現される。連結化では、グループによって創られたコンセプト(例えば、商品コンセプト)が、組織全体のレベルで、要素技術の形をとった既存の形式知と組み合わされ、新製品の形をとった形式知に体系化される。そして内面化では、再び個人(例えば、工場労働者、サービス・エンジニア、ユーザー)が、その製品を作ったり、メンテナンスしたり、使ったりすることによって、暗黙知としての新たなノウハウを蓄積するのである。
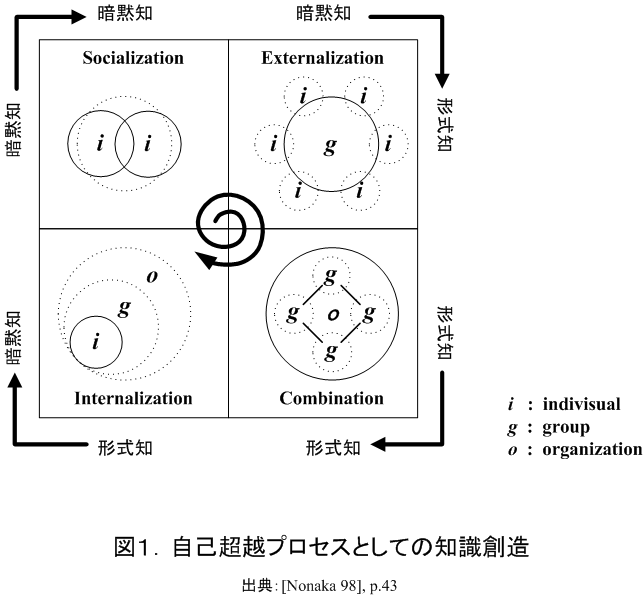
2.2 富士ゼロックスにおけるSECIモデルの実践
富士ゼロックスは、「知の創造と活用をすすめる環境の構築」をそのミッションの一つに掲げ、 ドキュメントを知の一つの分野として、「ザ・ドキュメント・カンパニー」を標榜している。この会社の海老名事業所では、「全員設計」というコンセプトに基づき、イントラネット上にZ-EISと名付けた知識共有システムを構築するとともに、開発プロセスすべての工程の担当者が三次元画像モデルを見ながら対話をおこなう「全員設計ルーム」を設けている。
この知識共有創造システムの開発は、開発期間延長の最大要因である最終段階での設計変更という問題を解決するために、1990年代の初めに開始された。それまでは、よりユーザーに近い視点を持つ後工程の担当者の意見を反映するためには、プロトタイプあるいは製品完成まで待たなければならなかったのである。このような問題を解決するために、各工程の設計者と技術者が相互交流 (interacting) をおこない、プロトタイプを前にして初めて明示的になることが多い、お互いの現場でのノウハウという暗黙知を獲得 (capturing) するために、互いの現場を訪問し合った(共同化)。
その中で、「初期設計の段階から、全員がコメントを出す、改善提案を出す、決定する、それぞれの領域で責任を持つ」という「全員設計」というコンセプトが生まれてきた。しかし依然として、いかにして獲得した現場の暗黙知を整理 (organizing)するか、という問題があった。この問題を解決するために、オンライン上の設計情報共有システムが開発され、Z-EISと名づけられた。そして設計者や技術者たちが、自分たちの体験知や設計ノウハウといった現場知を言葉にして、Z-EISにインプット(すなわち fomalizing)し始めた(表出化)。
しかし、インプットされた知識は、全員で共有すべきほど良いものばかりではない。そこで各工程の上司が、優れたものだけを特定 (identifying) し、登録するようにした。Z-EISには、そのような現場の知だけでなく、三次元画像モデル、部品仕様、市場データ、特許情報、製品管理データも含まれている。1999年現在で、4,500件の形式知化された設計ノウハウが登録・共有 (sharing) され、設計者500名、技術者4,100名が利用し、問い合わせ件数は毎月約50,000件にものぼる(連結化)。
登録されたノウハウが本当に有意義なものになるためには、それらが実際に活用され、実践に結びつかなければならない。したがって、言語化されたノウハウを効果的・効率的に活用するために、最も有用なものを選別 (selecting)し、「品質確立リスト」に編集して、デザイン・レビューに使っている。設計者は、この新しい体系的な形式知を、現場の状況に適応 (adapting) させながら、再び暗黙知として体得するのである(内面化)。
先に述べたように、このSECIプロセスはサイクルでなくスパイラルである。したがってそれは、拡大しながら、再び共同化のフェイズに入ってゆく。大きく豊かになった暗黙知を持った設計者と技術者たちが、全員設計ルームに集合し、そこで相互作用(interacting) を始めるのである。
野村と亀津 [野村99] によれば、現在広まっている単に既存の知識を共有・活用するだけのナレッジ・マネジメントの実践は、図2の右下半分に見られるように、形式化 (formalizing) から選択 (selecting) までのサイクルを構成するだけであり、いくらかの効率向上には貢献するかもしれないが、組織における創造性向上への貢献は期待できないのである。
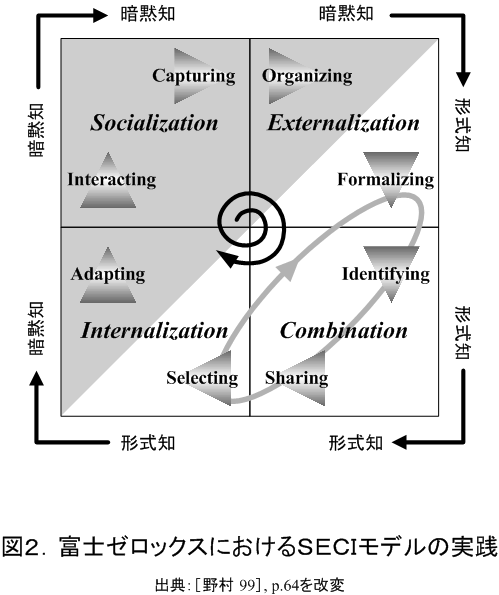
2.3 知識創造のための共有されたコンテクストとしての「場」
野中と紺野 [野中99] は、ナレッジ・マネジメントの分野に「場」 というコンセプトを導入した。場とは「その中で知識が創造・共有・活用される共有されたコンテクスト」と定義される。場には、オフィスのように物理的なものもあれば、テレビ会議のようにバーチャルなもの、共有された体験、思想、理想などのメンタルなものもある。
知識が創られるためには、コンテクストが必要である。知識を絶対的でコンテクストから自由であると見るデカルト流の知識観とは逆に、知識の創造プロセスは特定のコンテクストに依存せざるを得ない、と我々は考える。社会的・文化的・歴史的コンテクストは、情報を解釈し意味を創るときの基礎を提供する。情報は、場において解釈され、知識へと統合されるのである。また場は、個人が、知識変換の各モードに参加し、知識スパイラルを回すときの基盤(プラットフォーム)を提供する。
場を理解するときのキーコンセプトは、相互作用(インタラクション)である。知識は、たった一人で活動している個人によってではなく、個人間の相互作用ならびに個人と環境の間の相互作用によって創られる。相互作用は、リアルであったり、バーチャル(すなわちITベース)であったり、それらの組み合わせであったりする。特に共同化と表出化においては、同じ時間と空間で(すなわちリアルな場で)直接顔を会わせながら相互作用することが重要である。なぜなら、これらのモードは、電子的に伝達することが難しい暗黙知を取り扱うからである[梅本96, Nonaka 96]。場とは、相互作用し合う人たちによって共有されるコンテクストであり、その相互作用をつうじた自己超越と知識創造によって、場とその参加者が共進化していくのである。
場には、おおよそ共同化、表出化、連結化、内面化に対応した創発場、対話場、システム場、実践場の四つのタイプがある。
創発場は、顧客との接触あるいはトップの社内歩き回りのような、リアルな直接対面の相互作用で特徴づけられる。ここでは複数の個人が、体験、認知、感情を共有する。暗黙知を共有するときの重要な要因となる感覚や心理的反応を全面的につかまえることができるのは対面接触であるから、この場は共同化へのコンテクストを提供する。創発場は、個人が自己と他者の境界を超越し、他者に共感する世界であるという意味で、実存的な場所である。この場から、個人の間での知識変換の基盤となる思いやり(ケア)、愛(ラブ)、信頼(トラスト)、そして献身的態度(コミットメント)が生まれてくる。
対話場は、コンセプトを創造するプロジェクト・チームに見られるように、グループによるリアルな直接対面の相互作用によって特徴づけられる。そこでは、個人のメンタル・モデルが共有され、共通の言語に翻訳され、参加者間の対話によってコンセプトに明示化される。したがってこの場は、表出化へのコンテクストを提供する。また、グループによって言語化された知識は思索する個人に戻って行き、残りの暗黙知と相互作用を起こして、それらの更なる言語化を促進する。創発場と比較して、対話場は意図的に創られることが多い。対話場における知識創造を促進するには、可能なかぎり、特定の知識と能力を持った人たちを選んで集めることが鍵になる。
システム場は、イントラネットやグループウェア上でおこなう全社プロジェクトのように、間接的な(すなわちバーチャルあるいはITベースの)集団的な相互作用によって特徴づけられ、文書図面の形で大勢の人に簡単に伝達できる既存の形式知を結合するためのコンテクストを提供する。システム場を構築するためのバーチャルな協働環境を創るのが、テレビ会議やイントラネット、インターネットなどのITである。現在、多くの組織が、必要な情報や知識を交換したり、互いの質問に答え合ったり、効果的・効率的に情報・知識を集めたり広めたりするために、メーリング・リストやニューズ・グループなどのメディアを使っている。
実践場は、マニュアルによって学んだことを現場で実践しているときのように、形式知と行為との相互作用によって特徴づけられる。テキスト・マニュアルやビデオ・マニュアル、シミュレーション・プログラム、あるいはそれらの組み合わせによって伝達される形式知を実際にやってみることにより、個人はそれを暗黙的な操作知に体化するのである。言い換えれば、形式知を実際にあるいはバーチャルにやってみることによって学ぶのである。対話場では、言語が集団的内省を引き起こして集団的な自己超越に至るが、実践場では、行為が個人の内省を引き起こして自己超越に至る。
2.4 NTT東日本法人営業本部における場の構築
NTT東日本法人営業本部は、首都圏の大企業に対して、情報通信に関するソリューション・サービスを提供している。ここのナレッジ・マネジメントは、ソリューションという新たな知識を創造するために、リアルな場(すなわち独創的なオフィス・レイアウト)とバーチャルな場(すなわち本部社員およそ1,600名全員の個人ホームページと課、部、本部のホームページ)を組み合わせている点で注目に値する。
この革新的なナレッジ・マネジメント・プログラムを創ったのは、潮田邦夫副本部長である。このプログラムの背後には、彼の「開智」の思想がある。「開智」とは、英語のeducationがもともと「能力を引き出す」という意味を持っていることから、彼が独自に創り出したコンセプトであり、イントラネットと斬新なオフィス環境によって社員の能力を引きだそう、という彼の意図が込められている。
彼はまた、新しい知は職歴や技術のバックグラウンド、年齢、性別などが異なる人たちが出会うことによって創られるという意味の「クリエーション・バイ・クロス・カルチャー (Creation by Cross Culture)」というコンセプトを創り、そういう思いがけない「出会い」を起こすための対話がいつでも可能なオフィス・レイアウトをデザインした。
本部オフィスの各階は、次の四つのゾーンによって構成されている。
- 「ベース・ゾーン」は、主にプロジェクト・プランニングに使われ、個人の席を固定しない「フリーアドレス」が特徴である。社員は、出社するたびに、3種の神器であるノートパソコン、PHS、ワゴンを持って自分の座席を決め、イントラネット上でその場所を登録する。この仕組みは、プロジェクト・チームのすばやい編成、プロジェクト・メンバー間のスキルの共有(すなわち共同化)、隣の席に偶然すわることによる思いがけない出会いの促進を目的としている。したがってこのゾーンは、創発場とシステム場として機能する(図3参照)。

- 「クリエィティブ・ゾーン」は、プロジェクト・チームが、イントラネットからパソコンで引き出した資料を42インチ・ディスプレイで見ながら、対話によって新たなアイデアを創り出すのに使われる。このスペースは、開放的な雰囲気を持たせるために窓際にあり、移動可能な観葉植物で仕切られ、対話に参加する人数に応じて広さを変えることができる。したがって、このゾーンは対話場として機能する(図4参照)。

- 「コンセントレーション・ゾーン」は、クリエイティブ・ゾーンで得られたアイデアを発展させたり、イントラネットから得られた知識を自分の仕事に実際に使ってみる場所である。例えば、システム・エンジニアなどの個人が、プログラミングやシステム・デザイン、提案書作成のために使う。静かな環境で自分の仕事に集中したい個人のために、パーティションで区切られている。したがって、このゾーンは、システム場と実践場として機能する(図5参照)。

- 「リフレッシュ・ゾーン」は、喫煙室、ドリンク・コーナー、雑誌コーナーで構成され、一人でリラックスした気分に浸ったり、異なった背景を持った人たちが、インフォーマルに交流し対話するのに使われる。したがって、このゾーンは、創発場として機能する(図6参照)。

既存の知識を活用して新しい知識を創造するためのもう一つの仕掛けは、数多くのバーチャルな場としてのホームページである。約1,600人の本部社員の全員が、個人ホームページを持っている。それらは、「マイホーム」、「私の書斎」、「セカンドハウス」、「リゾートハウス」というメタファーで呼ばれるページから構成され、それぞれ以下のような内容が含まれる。
- 「マイホーム」は、ホームページを作った人の個人略歴、写真(あるいは動画)内線番号、電子メール・アドレス、血液型などの情報を載せた自己紹介のページである。
- 「私の書斎」には、営業日報、提案書、プロジェクト記録などの日常業務ファイルが置いてあり、営業本部社員であれば誰でもアクセス可能で、必要ならコピーしたり、わからない点があれば本人に問い合わせることもできる。
- 「セカンドハウス」は、個人の業務履歴、得意な業務分野、資格、これまで手がけてきたプロジェクト事例などが納められている。
- 「リゾートハウス」は、自分の趣味や家族のことなどを紹介するページである。
さらに、課や部もそれぞれのホームページを持っており、それらにさまざまな知識ベースを載せている。たとえば第三営業部は、営業提案書やプレゼンテーション資料などを登録した「智の森」と呼ばれる知識ベースを構築している。優れた営業ノウハウの共有を目的とするこの知識ベースは、以下のように使われている。
(1)営業マネジャーは、部下が毎日イントラネットを通じて提出してくる折衝記録と添付された提案書を読む。
(2)彼は、他の営業マンにも共有してもらいたい優れた提案書にコメントを付け、あるボタンをクリックして「智の森」に登録する。
(3)登録された提案書は、それぞれへのアクセス回数だけでなく、それを使って成果を得た人からの「感謝ボタン」のクリック数もカウントされ、ともに「智の森」のページにランキング表示される。
(4)最も人気の高かった上位二つは、半年毎に「ベスト・ナレッジ賞」として表彰される。
2.5 知識資産の四類型
企業にとって知識は、持続可能な競争優位を創るために最も重要な資産であるが、我々はいまだに、知識資産を測定・評価・管理するための有効な方法を持っていない。知識資産ないし知的資本(インテレクチュアル・キャピタル)を測定する新しい試みはいくつか提案されているが、 知識資産の一部の暗黙的かつ動態的な性質のために、それらを含めた既存の会計システムでは知識資産の価値を把握することは難しい。
しかし、知識戦略を創るためには、知識がいかにして創られ、蓄積され、活用されるか、についての何らかの理解が必要である。その試みの端緒として、野中と紺野 [野中99、Nonaka 00c] は、知識資産を経験的 (experiential)、概念的 (conceptual)、体系的 (systemic)、恒常的 (routine) の四類型に分類した。
経験的知識資産とは、創発場において、社員間あるいは社員とサプライヤーあるいは顧客との直接的な共有体験によって創られる暗黙知である。仕事上の経験をつうじて蓄積されるスキルやノウハウがその例である。他の例としては、ケアやラブや信頼といった情感知、顔の表情やジェスチャーなどの動作知、熱中や緊張などのエネルギー知、そして即興や引き込みといったリズム知などが挙げられる。経験的知識は暗黙知なので、捕捉や評価が難しく、金銭的取り引きが困難である。企業は、経験をつうじてのみ、この種の知識資産を蓄積できる。この暗黙的な性質が、この知識資産を模倣するのが難しい企業に特殊なものとし、持続可能な競争優位を企業に与えてくれる。
概念的知識資産とは、表出化の対話場から生まれてくる言葉、数字、図表、シンボルで表現された形式知である。企業の社員が保有している経営戦略、製品コンセプト、製品デザイン、あるいは顧客が保有しているブランドに対する知覚などがその例である。コンセプト知識資産は有形のものが多いので、経験的知識資産より目で捉えやすいが、社員や顧客の知覚は測定するのが難しい。
体系的知識資産とは、パッケージ化された形式知であり、明示的に表現された技術、製品仕様、マニュアル、顧客やサプライヤーについてまとめられた文書、特許やライセンスのように法的に保護された知的財産権(インテレクチュアル・プロパティ)などが、このカテゴリーに含まれる。この種の知識資産は最も捕捉しやすく、デジタル化も簡単なので、現在のナレッジ・マネジメントは、もっぱらこの種の知識資産に焦点を当てている。また、取り引きも移転も比較的たやすくできる。
恒常的知識資産とは、企業の日常活動に埋め込まれている暗黙知である。例えば、企業の職能別ノウハウや、組織のメンバーが共有している思考と行動のパターンとしての組織的な習慣や文化がその例であり、毎日の活動によって再生産されている。自分の会社についての物語を共有することは、この種の知識資産を形成するのを助ける。しかし、その恒常性が惰性に変わって、新しい知識の創造を邪魔する可能性もある。
2.6 富士ゼロックス、日立、ソニーにおける知識資産プログラム
前節で述べた類型はまだ新しく、これを実際に使って知識資産の管理・活用をおこなっている日本企業はまだ存在しない。しかし、知識資産の重要性を理解する企業はますます増えてきている。三つの日本企業の事例を紹介しよう。
富士ゼロックスは、いくつかの知識資産プログラムを設けている。最も興味深いのが、「Cクラス・マーケティング」と呼ばれる知識資産活用プログラムである。Cは、CEO(Chief Executive Officer最高執行責任者)やCKO (Chief Knowledge Officer知識担当役員)などのCであり、決定権を持っているトップ・マネジャーを意味している。このプログラムは、富士ゼロックスが長年にわたって蓄積してきたさまざまなテーマに関する知識資産を(失敗から得られた知恵さえも)、顧客企業のトップ・マネジャーに提供することにより、決定権を持った彼らに富士ゼロックスの営業マンが近づくのを助けようというものである。それらのテーマには、例えばトータル・クォリティ・マネジメント (TQM)、リスク管理、アウトソーシング、人的資源管理、営業部隊の情報武装などが含まれる。これらは、暗黙的な経験的知識資産を表出化した明示的な体系的知識資産であり、現在も富士ゼロックスで使われている。
このプログラムは以下のように作動する。営業マンが、顧客企業の営業窓口担当者に、「コラボレーション・プログラム」というタイトルのついた一枚の紙を手渡す。それには、上に挙げたようなさまざまな経営課題が列挙してあり、それらの「ノウハウについて、一度、話しを聞いてみませんか。必ずやお役に立つはずです」という口説き文句が書かれている。そして営業マンは、その企業のトップ・マネジャーを「コラボレーション・ルーム」と名づけた(現在、東京に5カ所、大阪と名古屋に一つずつある)プレゼンテーション・ルームに招待する。トップ・マネジャーたちに、彼らが関心を持っているテーマについてプレゼンテーションするのは、富士ゼロックスが社内で養成した各テーマの専門家である。社内アンケート調査によれば、「取引先との信頼関係がとても強くなった」と「強くなった」を合わせた回答は95パーセントに達し、「商談の進展にとても役立つ」あるいは「役立つ」と答えた比率は88パーセントに達したという。
知識資産を無料であげるのではなく、それをインターネットで外販しようとしているのが「知の事業化」をめざす日立製作所である。1998年、日立の社長になった庄山悦彦氏は、新聞の全面広告で「技術と知の総合力を発揮する知識企業を目指します」というキャッチフレーズを使って、日立の将来ビジョンを宣言した。それ以来、日立は二つの知識資産プログラムを設けた。一つは、それまで社内でしか使われてこなかった体系的知識資産、例えばコンピュータ支援エンジニアリング (CAE) ソフトを、インターネット上に開設したポータルサイト「iエンジニアリング」をつうじて会員向けに売ろうというものである。
もう一つは、今年の4月に社長室に設けられたブランド・マネジメント・プログラムである。それは、日立ブランドを戦略的に管理するために、その方向性を明示する「ブランド・プラットフォーム」を策定し、それを端的に表現するコンセプト「インスパイヤ・ザ・ネクスト」すなわち「次なる時代に息吹きを与え続ける」ことにより、「豊かな生活とよりよい社会」をめざそうというものである。このプログラムのもとで、日立グループ600社のブランド施策を統一的に管理し、ブランド使用料も徴収するという。目標は、ソニーブランドに匹敵するほどに、日立ブランドの価値とイメージを上げることである。
ソニーといえば、最近の新聞インタビューで出井伸之会長は、「ソニーならではの知的財産をベースにした知識製造業を目指す」 と宣言した。ここで言う知的財産とは、製造能力、ブランド・パワー、消費者についての知識を意味している。日本で異端児とされるソニーは、独自の組織文化を持っており、それを次世代に伝えるための「ソニー塾」と呼ばれる知識資産プログラムを設けている。それは、ソニーのトップが、毎年十数名の30代半ばの優秀な社員に、代々引き継がれてきた経験的知識資産としての「ソニーのパイオニア精神」を伝承する「場」であり、一方で、概念的知識としての経営戦略をトップに提言するプロジェクト・チームとしての「場」でもある。今年は7回にわたったプログラム最終日に、16人の塾生が4チームに分かれて、当時まだ社長だった出井伸之会長に、インターネット時代のソニーの経営戦略を提言した。出井氏は、「レベルの差はあるが、それぞれ使えるアイデアだ。すぐ実行するように」と即座に指示し、提言した塾生たちを驚かせた。
2.7 ナレッジ・リーダーシップ
知識創造プロセスは、情報の流れのコントロールに焦点を置いた従来のマネジメントのやり方でマネージすることはできない。しかし、いくつかの促進要因を提供することによって、「ナレッジ・リーダー」としてのトップとミドル・マネジャーは、組織が活発かつダイナミックに知識を創造するのを助けることができる[野中95, von Krogh 00b]。ナレッジ・リーダーとしてのトップ・マネジャーの任務は、(1)知識ビジョンを創る、(2)知識資産を絶えず再定義し、それらが知識ビジョンに合っているかをチェックする、(3)「場」を創り、それらにエネルギーを与え、いくつもの「場」をつなぐ、(4)SECIプロセスをリードし、促進し、正当化することである(図7を参照)。
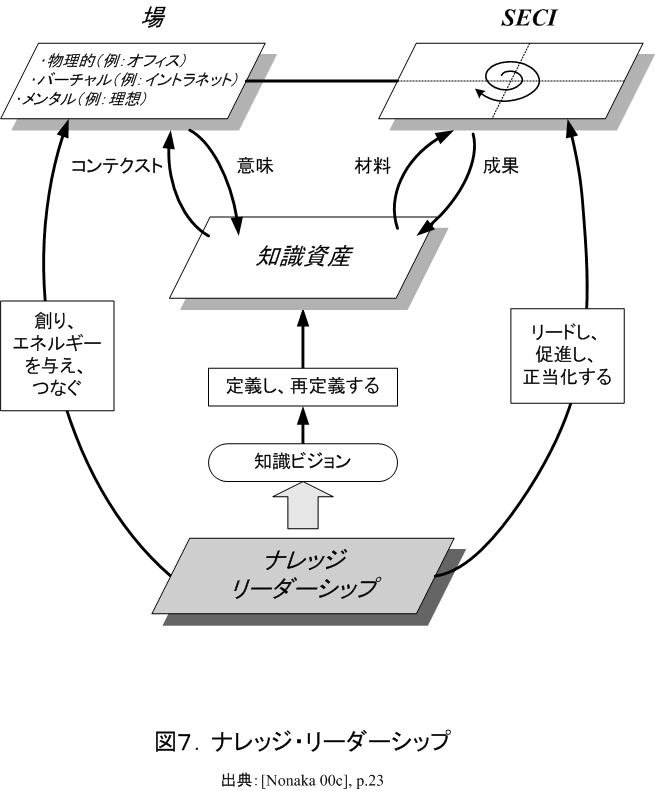
これらの任務はミドル・マネジャーの責任でもあるが、知識ビジョンを創ることだけはトップ・マネジャーの役割である。したがって我々は、ミドル・マネジャーを「ナレッジ・プロデューサー」と呼ぶことにする。新しい知識を創造するために、複数の「場」を創り、育て、率いるのが、組織の中で縦横の情報の流れの交差する戦略的地位に位置する彼らなのである。「ミドル・アップダウン・マネジメント」[Nonaka88, Nonaka 95, 野中96] は、知識創造プロセスを促進する「分散型リーダーシップ(distributed leadership)」の一例である。
2.7.1 知識ビジョンを提供する
知識を絶えず創造し続けるためには、組織全体を方向づけ、動かし、同調させる知識ビジョンが必要である。知識ビジョンを創り、それを社内外に広めるのは、トップ・マネジャーの役割である。知識ビジョンは、(1)どの領域で、いかなる知識を創るべきかを決める、(2)創った知識のタイプと質を評価し、正当化し、決定する価値体系を提供する、(3)知識創造プロセスに方向感覚を与える、(4)そのプロセスに参加する人たちの自発的なコミットメントを育む、(5)会社とその知識ベースが長期的にはどのように進化すべきかを決める、という機能を持っている。
知識そのものには境界がないので、既存の事業構造にかかわらず、企業はどのような知識も創ることができる。したがってトップ・マネジャーが、既存の商品、事業部、組織、そして市場の境界を超えるような知識ビジョンを提供することが重要である。ビジョンは、本質的にあいまいなので、誰かによって明示化される必要がある。トップが自分自身でやってもよいが、普通はトップの理想論的なビジョンとボトムと第一線社員の錯綜した現実との橋渡しをしているミドルに、その責任が下りてくる。彼らは、たいてい抽象的で壮大なコンセプトで表現されることが多いビジョンを、毎日の知識創造活動を導くより具体的な中範囲のコンセプトにブレイク・ダウンしなければならない。また彼らは、「ナレッジ・プロデューサー」として、そのビジョンに従って知識創造活動をリードしなければならない。
2.7.2 知識資産を定義する
全社レベルでナレッジ・マネジメントを視るポジションとして、CKO (Chief Knowledge Officer 知識統括役員)を置く企業が増えてきている。しかしこれまでは、既存の知識資産をいかに活用するか、というマネジメントが彼らの主な役割であった。これからの彼らの役割は、知識ビジョンを実現するために、いかなる新しい知識資産が必要とされるのか、ということを定義することによって、知識戦略策定をリードすることである。知識には限界というものがないが、一方で陳腐化するのも速いので、トップ・マネジャーは、自社にとってどのような知識が必要なのかを、絶えず再定義しなければならない。そのような創造的破壊のために、まず自社の知識の棚卸しをやった上で、知識を効果的・効率的に創造・蓄積・活用するための知識戦略を創らなければならない。例えば、環境にやさしい21世紀カーを開発するために、トヨタがガソリン・エンジンと電気モーターを組み合わせたハイブリッド・パワー・システムについて調べてみたところ、そのようなシステムを作るために必要な次世代の蓄電池、モーター、コンバーター、インバーターなどの重要な要素技術を自社では保有していないことがわかった。会社の命運を左右するような、そのように重要な知識の欠如に驚いたトヨタのトップは、そのハイブリッド・システムの研究開発に多大の投資をおこなった。その結果が、世界で最初のハイブリッド・カーであるプリウスに使われているのである。
2.7.3 場を創り、場にエネルギーを与え、場をつなぐ
場は意図的に創ることもできるし、自生的に創発してくることもある。トップ・マネジャーとナレッジ・プロデューサーは、会議室のような物理的スペースやコンピュータ・ネットワークなどのサイバースペース、あるいは共通のビジョンのようなメンタル・スペースを提供することによって、場を創ることができる。プロジェクト・チームのようなタスクフォースを創るのは、意図的に場を創る典型例である。正しいメンバー構成を選び、彼らの間のインタラクションを促進するのが、ナレッジ・リーダーの役割である。
また、自生的に生まれてきても短命ですぐに消えてしまうような場を発見・育成・活用するのも、ナレッジ・リーダーにとって重要なことである。そのためには、社員たちがお互いに、あるいは環境とどのように相互作用しているか、を見ながら状況を読まなければならない。さらには、そのような脆弱な場とそこにおけるSECIプロセスを支援するために、自律性、創造的カオス、情報の冗長性、最小有効多様性、愛(ラブ)、思いやり(ケア)、信頼(トラスト)、献身的態度(コミットメント)などの促進要因を与えて、場にエネルギーを注入しなければならない。
さらに、企業の知識ビジョンを促進するためには、いくつもの場をつなげてより大きな場を創る必要がある。そのためにナレッジ・リーダーは、場と場の相互作用と場への参加者間の相互作用を促進しなければならない。場と場の関係性は、事前に決まっていないことの方が多い。したがって場をつなぐためには、場と場の関係性が時間とともに展開していく状況を読みとる必要がある。
2.7.4 SECIプロセスをリードし、促進し、正当化する
ナレッジ・リーダーとしてのトップ・マネジャーの最も重要な任務は、全社レベルでの知識創造プロセスが知識ビジョンに向かっているか、そして創られた知識が知識ビジョンに照らして正しいかどうか、を絶えずチェックすることによって、SECIプロセスを統率する(すなわちリードし、促進し、正当化する)ことである。知識創造プロセスをコントロールして創造性を抑圧することなしに、時折そのプロセスの参加者に適正なアドバイスを与えなければならない。そして、そのプロセスが壁にぶつかっている時には、全体状況を見ながら、問題を解決するために自分でコンセプトを創らなければならない。
ミドル・マネジャーは、ナレッジ・プロデューサーとして、トップ、第一線社員、顧客、サプライヤーの暗黙知を掴まえ、それを新しいコンセプトに表出化する。彼らは知識創造プロセスに直接的に関わるので、新しいコンセプトを創り、自分の言葉で表現する高い能力が求められる。特に、自分のメンタル・モデルを豊富な語彙、メタファー表現、アナロジー推論、ビジュアル言語としての作図、そして非言語的ボディ・ランゲージで伝えることのできるコミュニケーション能力が大事である。
2.8 エーザイにおけるナレッジ・リーダーシップ
日本第5位の製薬企業エーザイは、かなり忠実に我々の組織的知識創造理論を実践している。1988年に内藤晴夫が社長に就任したとき、製薬業界は医療費の抑制、薬価引き下げ、海外企業の日本進出、他産業からの参入、研究開発費の増大、消費者の薬に関する知識の向上などの環境変化に直面していた。1989年に彼は、全社員に向けて「世の中変わります。あなたは変われますか?」という挑戦的な問いかけをおこなった。それは、社員の意識の変革を促すための「ゆらぎ」であり、それまでの自分、会社、仕事を見直すきっかけとなった。それが、「エーザイ・イノベーション」という企業変革運動の始まりであった。
その運動の開始にあたって、内藤は「患者様と生活者の喜怒哀楽を考え、そのベネフィット向上を第一義とし、世界のヘルスケアの多様なニーズを充足する」というエーザイの企業理念を発表した。それはまた、「ヒューマン・ヘルス・ケア」そのイニシャルを取ってhhcというコンセプトに集約されて、以後その運動の中味は、hhc活動と呼ばれるようになった。
hhc活動は、これまで3段階を経てきている。第一段階は1990-91年で、「エーザイ・イノベーション」を実現するために、内藤社長自らが全部門から選んだ社員103名を「コア・マネジャー」すなわちナレッジ・プロデューサーに育成した。第二期は、1992年からの5年間であった。コア・マネジャーたちは、全社員がhhcというコンセプトを理解し毎日実践していくという目標に向かって、74のhhcプロジェクトを立ち上げた。それらのプロジェクトは、製品を改良したり、顧客との関係を改善したりすることにより、患者のベネフィットを増大しようというものであった。それは知識創造活動であったが、当時はまだそれを意識してはいなかった。
1997年エーザイは、組織的知識創造理論を基礎にhhc活動を進めることを決め、まず「知創部」というナレッジ・マネジメント専門部署を設置した。知創部の役割は、(1)研修やイントラネット上のホープページ「知の広場」をつうじて、組織的知識創造理論を全社的に広める、(2)四つの知識変換モードすなわち共同化、表出化、連結化、内面化のそれぞれについて、全社とすべての部課ごとの能力をアンケート調査で評価し、弱いところがあれば、それの強化策を提言する、(3)エーザイ・イノベーション運動とhhc活動を推進し、その成果を全社に伝える、(4)「ナレッジ・ワーカー」を育成するためのプログラム(一部は有料)を立案・実行する、というものである。
数あるhhcプログラムの中で最も興味深いのが「ナレッジ・プロデューサー」育成を目的としている4回シリーズの「hhcコンファランス」である。それには、内藤社長自ら選んだ優秀な社員が参加する。その内容は、(1)知識創造スキル、特にコンセプト創造スキルを開発するためのコース、(2)経営革新と戦略思考を議論するコース、(3)患者の暗黙知を捉える共同化のための病棟実習、(4)参加者によるトップへの革新提案発表会、(5)以上でカバーしきれない形式知を学ぶ通信教育の五コースから構成されている。
このように、エーザイでは、トップが知識を正当化する際の判断基準となる企業理念を提唱し、またそれを端的に集約したhhcというコンセプトを創造するなど、ナレッジ・リーダーシップが充分発揮されており、ミドル・レベルでも(我々の言葉そのままに)「ナレッジ・プロデューサー」を意図的に育成しているのである。
3.おわりに
ハンセン・ノーリア・ティアニー[Hansen 99, 邦訳ティアニー99]は、一昨年のハーバード・ビジネス・レビューで、ナレッジ・マネジメント戦略には次の二つのタイプがあると論じた。すなわち、「知識が注意深くコード化されてデータベースに蓄積され、社員全員が容易にアクセスして利用できるようにする」コード化戦略(codification strategy)と、「知識はそれを創り出した人に密着しているので、人と人が直接会うことによって共有」することをめざす個人化戦略 (personalization strategy)である。彼らはまた、二つの戦略の同時追求は企業業績に悪影響を与える、と論じた。
しかし、彼らが個人化戦略の事例として取り上げているマッキンゼーやボストン・コンサルティング・グループ(BCG)は、最近のビジネスウィークによれば、「世界で最も高性能で高価格の社内用データーベースを設置した」 そうである。また、ダベンポートとプルサック[ダペンポート01]によれば、彼らがコード化戦略の例として取り上げているアンダーセン・コンサルティングは、人と人が直接対面するコミュニティの形成を積極的に進めているという。さらに、彼らの分類に従えば、暗黙知重視の日本企業は個人化戦略を採ってきたということになろうが、我々が観察してきた日本企業は、積極的にITを活用している。ヨーロッパでも、ジェミニ・コンサルティングやノキア などが、同じような混合戦略を採っている。
つまり、二つの戦略のどちらかを選べ、ということではないのである。今では、アメリカで一般的なITベースすなわち形式知志向のナレッジ・マネジメントと、日本でこれまで見られた人間ベースすなわち暗黙知志向のナレッジ・マネジメントは、互いの方向に近づきつつあるように見える。将来は、バーチャルな場とリアルな場をどちらも等しく活用するようなナレッジ・マネジメントに収斂していくのかもしれない。
いずれにせよ、ITは、既存の知識の共有・活用すなわち「知識管理」に大いに貢献している。しかし、最初に言ったように、ナレッジ・マネジメントの目標は新しい知識を絶えず創造し続けること、すなわち「知識経営」である。我々は、その知識創造を助けてくれるようなIT(特にAI技術)の更なる発展に期待している。
参考文献
[Davenport 98] Davenport, T.H. and L. Prusak: Working Knowledge: How Organization Manage What They Know. Harvard Business School Press, 1998. 梅本勝博(訳)ナレッジ・マネジメント:知を活かす経営、生産性出版、2000.
[ダベンポート01] T.M.ダペンポート、L.プルサック:ナレッジ・マネジメント:今後の課題、本号所収、2001.
[Edvinsson 97] Edvinsson, L., and M. S. Malone: Intellectual Capital. New York: Harper Business, 1997.
[エドビンソン99] L.エドビンソン、マイケル・S・マローン、インテレクチュアル・キャピタル、高橋透(訳)、日本能率協会マネジメントセンター、1999.
[Hansen 99] Hansen, M.T., N. Nohria, and T. Tierney: "What's Your Strategy for Managing Knowledge?" Harvard Business Review, March-April, pp.106-117, 1999. 邦訳は [ティアニー99].
[金澤 00] 金澤傑:知識創造における場に関する実証研究〜N社法人営業部門の事例〜、北陸先端科学技術大学院大学 知識科学研究科 修士論文2000.
[Leonard-Barton 92] Leonard-Barton, D.: "Core Capabilities and Core Rigidities: A Paradox in Managing New Product Development," Strategic Management Journal, 13-5, pp.363-380, 1992.
[森田00] 森田宏:エーザイ知創部について、北陸先端科学技術大学院知識科学研究科ケース・スタディ草稿、2000.
[西田91] 西田幾多郎:善の研究、ワイド版岩波文庫、1991.
[野村 99] 野村恭彦、亀津敦:統合的ナレッジ・マネジメント・システム構築のためのフレームワークに関する一考察、ナレッジ・マネジメント研究年報、第1号、pp.55-72, 1999.
[Nonaka 88] Nonaka, I. "Toward Middle-Up-Down Management: Accelerating Information Creation," Sloan Management Review, 29-3, pp.9-18, 1988.
[野中90] 野中郁次郎:知識創造の経営、日本経済新聞社、1990.
[Nonaka 98] Nonaka, I. and N. Konno (1998). "The Concept of 'ba': Building a Foundation for Knowledge Creation," California Management Review , 40-3, pp.40-54, 1998.
[野中99] 野中郁次郎、紺野登:知識経営のすすめ、ちくま新書、1999.
[野中96] 野中郁次郎、竹内弘高(著)、梅本勝博(訳):知識創造企業、東洋経済新報社、1996.
[Nonaka 95] Nonaka, I. and H. Takeuchi: The Knowledge-Creating Company. New York: Oxford University Press, 1995.
[Nonaka 96] Nonaka, I., K. Umemoto, and D. Senoo: "From Information Processing to Knowledge Creation," Technology in Society, 18-2, pp.203-218, 1996.
[Nonaka 00a] Nonaka, I., P. Reinmoeller, and D. Senoo: "Integrated IT Systems to Capitalized on Market Knowledge," in von Krogh, I. Nonaka, and T. Nishiguchi (eds.), Knowledge Creation: A Source of Value, London: Macmillan, pp.89-109, 2000.
[Nonaka 00b] Nonaka, I., and P. Reinmoeller, and R. Toyama: "Integrated Information Technology for Knowledge Creation." In Dierkes, M. and et al (eds.). Handbook of Organizational Learning and Knowledge, Oxford: Oxford University Press, 2000.
[Nonaka 00c] Nonaka, I., R. Toyama, and N. Konno:"SECI, Ba and Leadership: a Unified Model of Dynamic Knowledge Creation." Long Range Planning, 33, pp.5-34, 2000.
[Nonaka 00d] Nonaka, I., R. Toyama, and A. Nagata: "A Firm as a Knowledge-Creating Entity: A New Perspective on the Theory of the Firm," Industrial and Corporate Change, 9-1, pp.1-20, 2000.
[NTT 00] NTT東日本法人営業本部CRM&CTI推進室: 実践CRM構築、NTT出版、2000.
[清水99] 清水博:新版 生命と場所、NTT出版、1999.
[Stewart 97] Stewart, Tom: Intellectual Capital : The New Wealth of Organizations. New York: Doubleday, 1997.
[ティアニー99] トーマス・ティアニー、ニティン・ノーリア、モーテンT.ハンセン:「コンサルティング・ファームに学ぶ『知』の活用戦略」ダイヤモンド・ハーバード・ビジネス, 24-5, 1999.
[梅本96] 梅本勝博、妹尾大:情報処理から知識創造へ-情報技術と企業経営の新しいパラダイム-、オフィス・オートメーション、16-5、pp.67-74, 1996.
[von Krogh 97] von Krogh, G., I. Nonaka, and K. Ichijo: "Develop Knowledge Activists!," European Management Journal, 15-5, pp.475-483, 1997.
[von Krogh 00a] von Krogh, G., I. Nonaka, and T. Nishiguchi (eds.) Knowledge Creation: A Source of Value. London: Macmillan, 2000.
[von Krogh 00b] von Krogh, G., K. Ichijo, and I. Nonaka: Enabling Knowledge Creation: How to Unlock the Mystery of Tacit Knowledge and Release the Power of Innovation. New York: Oxford University Press, 2000.
人工知能学会誌 第16巻 第1号 2001年1月 pp.4-14.
Copyright 2000-2008 Umemoto-Lab. All rights reserved.