
スタートアップと技術戦略の研究から
産業・政策への貢献を目指す
科学技術イノベーション研究室
Laboratory on Science and Technology-based Innovation
教授:奥山 亮(OKUYAMA Ryo)
E-mail: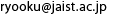
[研究分野]
創薬エコシステム、新薬研究開発マネジメント、科学技術イノベーション
[キーワード]
医薬品研究開発、技術経営、ディープテック、スタートアップ、産学官連携、イノベーション、エコシステム
研究を始めるのに必要な知識・能力
社会人が大学院で学ぶ大きな意義の一つは、実務上の課題を解決したり、自身の関心を深めたりする中で、知識や思考力を高めていくことにあります。何のために大学院で学ぶのかという明確な目的意識を持って研究に取り組むことで、学びはより実りあるものとなり、実務やキャリアにおいても大きな成長につながるはずです。
この研究で身につく能力
近年のビジネス環境は変化に富み、グローバル競争が加速しています。研究を通じて、課題を的確に認識し、機会を迅速に捉えて戦略立案やプロジェクト提案につなげる分析力と企画力が養われます。また、論理的思考力やプレゼンテーション力を高めることで、交渉力や提案力といった、新たな価値創造に不可欠な能力も身につきます。さらに、試行錯誤を通じて、柔軟な発想力、チャレンジ精神、困難に立ち向かうレジリエンスも磨かれます。
【就職先企業・職種】 コンサルティング、製造業、行政職員など
研究内容
1.創薬スタートアップやエコシステムの研究
創薬に代表される科学技術イノベーションでは、大学等での研究成果が製品開発に高く活用されます。世界では、こうしたディープテックの実用化の多くを大学発等のスタートアップが担っていますが、日本はスタートアップが十分成長しておらず、新薬研究開発の国際競争力が低下しています。当研究室では、グローバルでの創薬におけるスタートアップの役割や国による貢献度の違い、それらが創薬イノベーションに与える影響について研究しています。近年急速に科学技術力を増している中国や一部新興国の動向にも着目し、グローバルでの医薬品産業構造の変化を分析しています。
スタートアップが成長するには、大学や大学研究者、起業家、投資家、政府や地方自治体、既存企業といったステークホルダーが有機的に連携するスタートアップ・エコシステムの役割が重要です。既存大企業が研究開発をリードするイノベーションシステムで発展し、固有の社会慣習や商習慣を有する日本が創薬等のディープテックで産業競争力を向上させるには、日本に合った独自のイノベーション・エコシステムを構築する必要があります。当研究室では、創薬スタートアップや産学官連携の定量・定性分析を通じて、日本のエコシステム強化に資するイノベーションマネジメントを追求し、実務家や政策担当者への提言につながる研究成果を目指しています。
2.新薬研究開発マネジメントの研究
新薬創出をめぐるグルーバル競争は年々激化しており、近年では核酸医薬、遺伝子・細胞治療、次世代抗体、中分子などの新たな医薬モダリティの技術革新が創薬力の鍵となっています。また、中枢疾患や希少疾患などアンメット・メディカル・ニーズが高く残る疾患領域の研究が注力されています。さらに、人工知能(AI)を活用したAI創薬など異分野技術との融合も進んでいます。当研究室では、こうした技術・市場環境の変化を分析し、企業の技術マネジメント、研究開発戦略、アライアンス戦略のあり方を探求しています。
主な研究業績
- Okuyama R. Increased contribution of small companies to late-entry drugs: a changing trend in FDA-approved drugs during the 2020s. Drug Discovery Today, 2024, Vol.29(2), 103866
- Okuyama R. Leveraging Corporate Assets and Talent to Attract Investors in Japan: A Country with an Innovation System Centered on Large Companies. Journal of Risk and Financial Management, 2024, Vol.17(12), 539
- Okuyama R. mRNA and Adenoviral Vector Vaccine Platforms Utilized in COVID-19 Vaccines: Technologies, Ecosystem, and Future Directions. Vaccines, 2023, Vol.11(12), 1737
研究室の指導方針
良い研究には、自らの問題関心を研究可能な問いへと落とし込む力と、それに答えるリサーチデザイン、適切なデータ収集・分析力が求められます。当研究室では、研究室ゼミや個人面談を通じてこうした研究遂行に必要な力の習得を支援します。自身の関心を深めながら、論理的な思考力や他者を納得させる提案力を養い、社会に新たな価値を生み出す人材の育成を目指します。メンバー同士が協力し、互いにに高めあう環境づくりにも力を入れます。
[研究室HP] URL:https://fp.jaist.ac.jp/public/Default2.aspx?id=796&l=0