| faculty |
| Kunifuji Lab. |
| Fujinami Lab. |
M2
Fujinami Lab.
- M2
・Satoshi SHOJI 庄子 哲 HP管理係 ・Fuminori TAKANO 高野 文徳 ・Shuuhei TAKIMOTO 瀧本 周平 ・Isao WATANABE 渡辺 功
- M1
・Yoshiko YABE 谷部 好子
| 庄子 哲 Satoshi SHOJI s_shoji@jaist.ac.jp  |
対話における働きかけと応答についての類型化 近年、統計的手法による自然言語処理、音声処理の成功にともない、コーパスに対してさまざまなタグ付けが行われている。対話コーパスに付与されるタグとしては、1.形態素タグ 2.構文タグ 3.意味タグ 4.談話タグ の4階層に分類される。大規模なコーパスに対してタグ付けを行なうには、人手による労力を軽減するために解析ツールによる出力を人手によって修正することが効率的である。形態素タグや構文タグといった統語レベルのタグには汎用と言えるタグ体系と、それに基づく解析ツールが存在する。しかし、談話タグは、人手で付与することが多く、多くの労力を必要とする。そこで、形態素、構文情報を記述した統語レベルのタグの付いたコーパスから働きかけと応答についての談話タグを推定するアルゴリズムを考案し解析ツールを作成する。分析の対象は働きかけと応答が典型的にあらわれる旅行相談、交通案内などの協調的問題解決の対話に絞って行なう。 人との共感。それは、ぼくにとっては、光であり、同時に、闇でもあります。はたまた、登るべき高き山であり、同時に、落ちてはならない深い穴でもあります。 たとえていうならそれは、脳において密やかに神経細胞を産み出し続ける海馬のようなものかもしれませんし、あるいはこの世のすべてを結びつける瞬間接着剤にも似た存在といえましょう。大いなる神秘に対してぼくは言うべきことばをなにも持っていないというのが真相ではありますが、ただし最近はかなり市場も安定化してきておやすく手に入るようになってきたのも事実ですね。そろそろ買い時かと思います。だからコミュニケーションについて研究しているのかもしれません。 |
| 高野 文徳 ftakano@jaist.ac.jp 
|
情報検索システムにおける余剰語を用いた自然な応答の生成方式 音声インタフェースをもった情報検索システムの待ち時間の有効利用と, 利用者の理解を助けるために, 結果の出力に余剰語を付加する. 電話などの音声のみで情報をやり取りする対話形式の情報検索システム(道案内など )での一対一対話において, 対話者が人間(理解者)とコンピュータである場合, コンピュータの発話に余剰語を付加する. 余剰語の出現頻度により, 理解者側の理解が高まったか, 自然な応答となっているかをアンケートを用いて調べる. 余剰語を含む自然な応答を生成するためのアルゴリズムを提案する. また, 自然性の評価方法についての考察, 検討もおこなう. 高野文徳(0x17, male). クラゲは好きですか? |
| 瀧本 周平 tkmt@jaist.ac.jp 
|
遺伝的アルゴリズムによる複数エージェント間の協調 作業の学習 複数のエージェントがいかにして協調し学習して協調関係を うまく構築するかという問題を、遺伝的アルゴリズムを用いて 解く可能性を示し、その過程を研究します。その題材には ”サッカー”を用い、最適なポジショニングを見つけながら ゴールを目指すというエージェント間の協調関係をどのように 構築するかという観点から、最も効率の良い手順を実験を 通して探り出したいです。 イタリア代表とインテルをこよなく愛する男です。 |
| 渡辺 功 isao_w@jaist.ac.jp 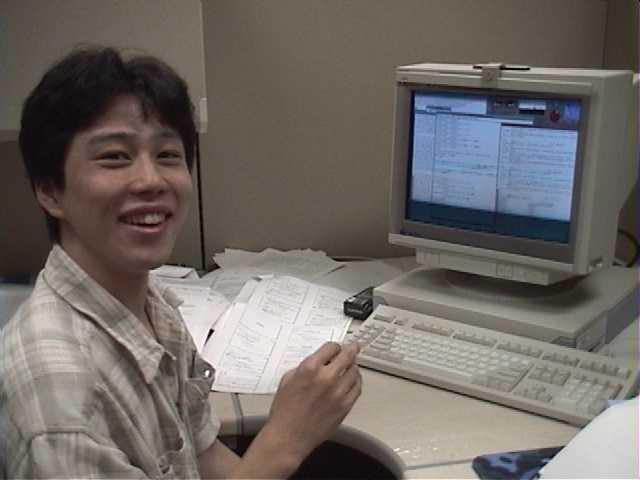
|
音声インターフェイスを用いたJAIST内PHSナビゲーションシステムの構築 JAIST内の教官数が多いため,教官に対する訪問者数は激増している. その訪問者は,JAIST内が巨大であるため戸惑いが生じている. これにより,目的とする教官を探すのに時間がかかる問題がある. それに付け加え,教官のスケジュールは大変込み合っていることが多い. また,飛び込みで用事が入ることもしばしばであり, それが分かるのはドアの前に立ってからである. そこで,JAIST内のナビゲーションシステムを構築することにした. 目的とする教官に会うためのルートを探し,それを教えてくれるシステムである. ユーザはPHSのみを使用するため,音声インターフェイスを組み込むことにした. 位置情報を示すPHSを持たない教官に対して,行動推論システムを実装する. ユーザインターフェイスについては,ユーザがストレスを受けないものを目指す. 情報科学科からこの知識科学科に来ました.興味本位で入りました. 人工知能に興味を持っていたので,副テーマもそれに準ずることをしました. ここの先生方は学問に関して幅広いバックグラウンドをお持ちですので, とても参考になりました.主テーマでは,開発に近いことをしています. 主テーマを行う時間があまりないので残念ですが,よい結果を残そうとがんばっています. 趣味は車関係ですが,忙しい毎日で愛車をかまってあげる暇がありませんでした.他にスキー,スノーボードや旅行も好きです. スキー場は車で10分で行ける所にあるので,助かると思いました. |
| 谷部 好子 y-yabe@jaist.ac.jp 
|
興味の対象は美学・詩学です。表現されたことが解釈されるのは、 どんなことなのか、知りたく思っています。 たとえば、元禄時代に連句という韻文の形式が完成しました。この 文芸の作品は、複数の作者たちにより制作されます。作者たちは、 ほかの作者が作った句に続く句を考えます。その過程で、句は次々 に違う解釈を受けなくてはなりません。その句の読み手が予期しない 新解釈で、新しい世界が次々に作られます。 解釈について考えるとき、私は連句におけるそれを思い出します。 この文芸は特殊ですが、それでも、表現者の意図が完全に読み手に 受け止められるということの不確実さは、他の表現、他の芸術でも同様 です。それなら、表現とは一体何なのでしょうか。 もちろん、以上のことを直接研究して行くわけではありません。この 疑問に近づく手がかりが、研究を通じて得られればいいと思っています。 どのように研究を進めるかはまだ固まっていません。あるプログラムを 作り、被験者にそれを触らせ、データを集める、ということを想像すること はありますが…。目下、資料を読み、読んだことを頼りにWebで調べると いう作業をしています。 3月までは東京のすみっこにある大学の哲学科研究室で、 かび臭い本と分厚い漢漢辞典を相手に生活していました。 テキストとひたすら向かいあうことが研究だったので、 まだここの知識科学っぽい方法にはなじんでいません。 当分は暗中模索です…ので、皆様どうかよろしく。 最近、カタツムリを飼い始めたのですが、どのような葉っぱを 食べさせたら栄養のバランスが取れるのか、いつも悩んでいます。 ご存知の方、教えてください。 |