| faculty |
| Kunifuji Lab. |
M2
| Fujinami Lab. |
Kunifuji Lab.
- M2
・Sadanori ITO 伊藤 禎宣 HP管理係 ・Takahiro KAWAJI 川路 崇博 宴会係 -> Calender ・Ryuki SAKAMOTO 坂本 竜基 ・Go SHIMIZU 清水 剛 ・Takafumi SEMIZUKI 勢見月 隆文 ・Akio TOMITA 富田 章夫 ・Katsuaki NAKAMURA 中村 勝明 ・Jian LI 李 健 ・Masaki KONDO 近藤 真己
- M1
・Shigeto OZAWA 尾澤 重知 ・Shuzo KANEKO 金子 修三 ・Tomonori KUBO 窪 智紀 ・Chikara SAITO 斎藤 主税 ・Kousuke SHINODA 篠田 孝祐 ・Asumi SHINOHARA 篠原 明日美 ・Kenji NAKAYAMA 中山 賢二 ・Satoru NAGAYAMA 永山 覚
| 伊藤 禎宣 sito@jaist.ac.jp 
|
コミュニティアウェアネスを支援するインフォーマルコミュニケーションツールの研究 近年、ネットワークにおけるインフォーマルコミュニケーションの支援を目的とした、ソーシャルウェアという概念が提唱されている。ソーシャルウェアでは、既存のグルー プウェアとの差異の一つとして潜在的コミュニティの顕在化支援機能の必要性をあげて いるが、その実現・評価研究は少ない。 本研究は、潜在的コミュニティを顕在化させ、インフォーマルコミュニケーションを 支援するシステムを構築・評価することを目的とする。具体的には、構成員間の関係構 造を仮想三次元空間に表示し、その空間配置状態の変遷を動的に表示することで、コミ ュニティとその構造的変化に関するアウェアネス(コミュニティアウェアネス)を支援 する。 ユーザは、空間配置状態の時間的変遷の結果に、可視化された現在のコミュニティ構造 を見ることができる。また、初期の空間配置や配置の変化量に現実社会での関係性等を バイアスとしてかけることで、初期状態が示す関係性と形成されたインフォーマルコミ ュニティにおける関係性との構造的差異を動的に表現することが可能である。 これにより、ユーザに対して、観点の相違に基いたコミュニティの静的及び動的な評価 とコミュニティへの適切な参加を促すことができる。 学部は法哲学専攻。話題の中心は二つ、生命倫理と知的財産権。現在の研究は上記の通り。 |
| 川路 崇博 tkawaji@jaist.ac.jp 
|
ブレインライティング法を用いたグループ発想支援ツールの研究 発想とは自分の獲得している知識から生まれるものであるが,個人発想にいきづ まり,それ以上の発想を得ようとする状態を考えると,同じ目的を持つ他人のアイ デアを参照することにより自分の頭の中の明確でないものを具体的なアイデアとし て連想できる場合が ある.このプロセスにブレインライティング法(以下BW法)を用 いることにより,時間という強制力と他人のアイデアから新たな発想を得ることが 期待される.既存のBW法では,参照できるアイデアの 数は回覧されてきたシート 上のものだけである.また発想の過程に おいてアイデアを自由に配置することがで きず,収束的思考の際の発想の妨げになっていた. そこで,すべてのアイデア が出され次第参加者に見せることによ り,より活発に連想させ,また発想を促すた めに関連すると思われる他人のアイデアを,任意の場所に空間配置できる個人的 ワークスペースを提供することにより,強制連想を促すグループ発想支援ツ ールを 構築することを研究目的とする. 世間で言うところの田舎からこちらにやってきたので、違和感はなかったのですが、 いわゆる都会と呼ばれる地域からこちらに来られた方々とは根本的に思考が違うと いうことを、いい意味でも悪い意味でも考えさせられました。学習環境はあまりに過 剰で、使いこなせない自分が腹立たしく思えることもしばしばです。 |
| 坂本 竜基 skmt@jaist.ac.jp 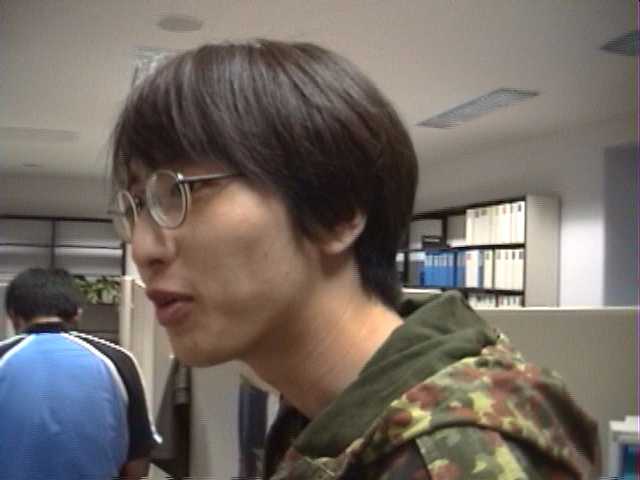
|
WWW空間上の知識共有を促進するコラボレーションツールの開発 現在,WWW空間上には膨大な情報や知識が散らばって存在しており,それらを効率よ く共有することの支援はグループウエアを構築する上で有効であるばかりでなく,こ れからのネットワーク社会においても重要な課題です. しかし,WWW空間はその特性上,構造を把握することが難しいため必要な情報の所在 やそれらの位置関係を知ることが困難な状況にあります. そこで私は,WWWにおける情報の共有化,WWW空間の共有,探索過程でのコラボレー ション支援などにより,単純な情報にとどまらずWWWが持つ多角的な意味やコラボ レーション過程で発生するアウェアネスなどを獲得,共有できる環境の開発を研究の 目的といたしました. この研究は従来のグループウエアが対象としてきた,データ共有や作業空間共有ばか りでなく,コミュニケーションに重点を置いているのが特徴であり,いわゆる「ソー シャルウェア」の考え方に近いものと捉えております. 私は大学で情報科学を専攻しており,主に並列プログラミングやシステム管理,ネッ トワーク技術などの修得に力を注ぐとともに,卒業までに第一種情報処理技術者試験 の資を取得いたしました.学部卒業後,平成10年度から立ち上がった本校の知識科学 研究科の第一期生として入学し,それまで勉強不足であった人工知能の分野や社会科 学系の知識といったものを主に修得してまいりました.現在は,学部時代に培った情 報科学の知識と本校で学んだ多様な知識をベースにし,グループウエア関係の研究に 力を注いでおります. |
| 清水 剛 gshimizu@jaist.ac.jp 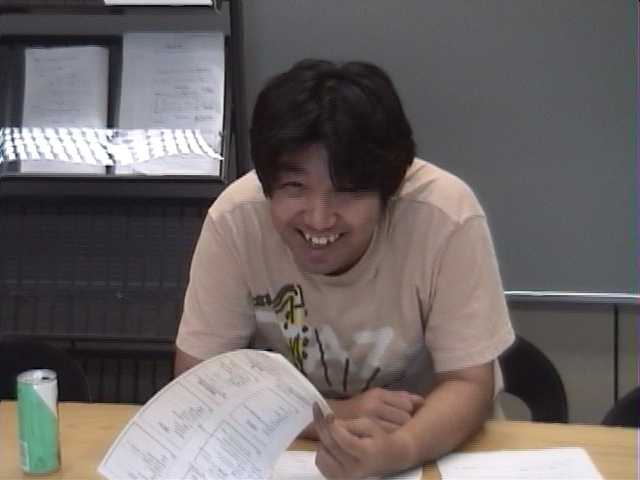
|
まちづくりプランニングにおけるKJ法とSD法による思考プロセスの分析 社会が多様化、複雑化してきている中で、その組織間の知識の差異が問題として表面化してきている。特に住民・行政・企業・大学は、まちづくりという共通目的を持っているが立場や視点、価値観やイメージなどに違いがある。その違いから生まれる緊張感、自発性、不信感といった情意的作用が知識の差異を生む。本研究ではまちづくりというプロセスにおいて組織間の情意的相互作用が、発想プロセスの発散的思考(関係がある事柄の現状把握)と収束的思考(関係の整理・本質追求)の二つの過程に影響するという仮説を立てる。全組織が対等な立場にある場合と一組織がリーダーシップをとった場合の思考プロセスを分析し、比較評価実験することを目的とする。 学内設備の充実もさることながら、仲間の発想の豊かさに驚き、楽しませてもらっています。勉学に関しては、今現在、文系出身の私が複数の理系教科を学ぶことはかなりの苦痛(笑)となっていますが、「研究したい」と思う者ならば、個々の情熱と努力次第で何でもできそうな気がしてきます。人間観察という点でも面白いところだと思いますよ、JAISTは。 |
| 勢見月 隆文 tsemizuk@jaist.ac.jp 
|
プロジェクト管理方法論DTCN/DTCをもとにしたプロジェクト管理支援ソフトウェアの構築とその評価
Design To Customers' Needs / Design To Cost(以下DTCN/DTC)は、朝日大学の江崎通 彦教授が考案されたプロジェクト管理の方法論である。ユーザはDTCN/DTCを用いることで 、他の方法論よりプロジェクト進行の効率化や迅速な問題解決が期待される。DTCN/DTC法 は、現在のところ問題を手作業で解決している。DTCN/DTCをより迅速に再利用可能な形に するために、そのコンピュータ支援ソフトウェアとユーザインターフェースを構築する。 評価方法として、DTCN/DTC法を周知の研究室の学生や大学教官などをユーザ層として想定 した、エンドユーザによる評価テストをおこなう。すなわち、支援ソフトを使った場合と 使わない場合の対照実験による定量的評価と、アンケートによる定性的評価をおこなう。 なんだか変な感覚です。専門がばらばらなのに、「みんなとは違うことをやりたい」と考えている人がほとんどで、研究室にいて人と話をするととっても妙な気分です。良くも悪くもいわゆる常識を超越しているので、古くさい考えに馴染めない人にはぴったりかと。はい。 ただ、先ほども書いたように集まってきている人々の専門が多方面に渡っている関係上、どうしても講義もPrologから会社のケーススタディまでと、多方面になってしまい、理系出身者は経営、経済系が苦手、文系出身者の大半は物理と情報がダメ、とコンスタントに成績を取るのは非常に厳しいです。おそらくこれほど異分野の専門をカバーしている研究科は日本初だろうと思われます。 そのため、講義で追い詰められてくると、「つまるところ、生活できるだけ稼げばいいんだろ、こんちくしょ〜」という究極の目的に頭がいってしまうことも。 とりあえず、研究の遅れを設備の貧弱さに責任転嫁できないくらいそれなりの環境が整っているので、スパコンから先生の頭までフルに活用すれば、結構な研究ができる、はず。。。 けど、必修多すぎ。自分の創造に時間割けないじゃん。 |
| 富田 章夫 atomita@jaist.ac.jp 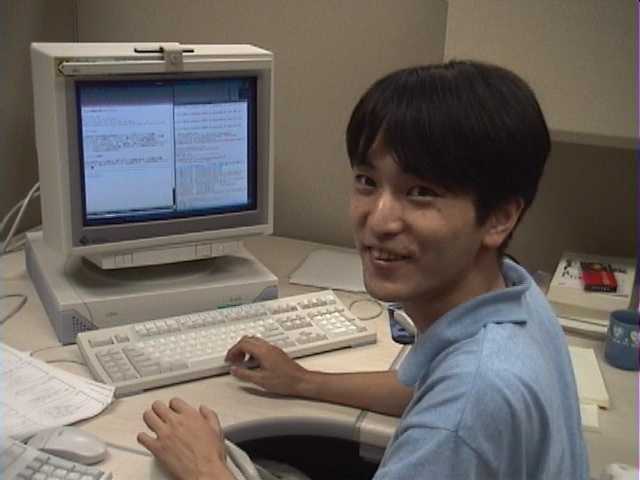
|
エージェントによるグループ意思決定を支援するWebアウェアネス環境の構築 時間や空間の共有を必要としないコミュニケーションの場をもとにしたネット ワーク社会が存在します。そうした場でグループ意思決定を行う場合、人間の 意思を代理するエージェントを介すると、グループの構成員間のネゴシエーシ ョンを行うことができます。 ここでは、そのような場面を想定して、ネットワーク上に散在する商品カタロ グの収集、購入物品の決定を行うことができる意思決定支援グループウェアを エージェントをもちいて実現します。その中で、人間の嗜好の分析をし、合意 形成を促進する、といったグループ意思決定を支援する環境を実現します。 また、エージェントに議論を代理させる環境を考慮したWebアウェアネス支援に もとづくコラボレーション環境を実現します。 これにより、ネットワーク社会における意思決定を積極的に支援することがで きるWWWコラボレーション環境を構築することを目的とします。 人の活動を積極的に支援するコンピュータ」に惹かれている夢見がちな青年。 |
| 中村 勝明 katsuaki@jaist.ac.jp 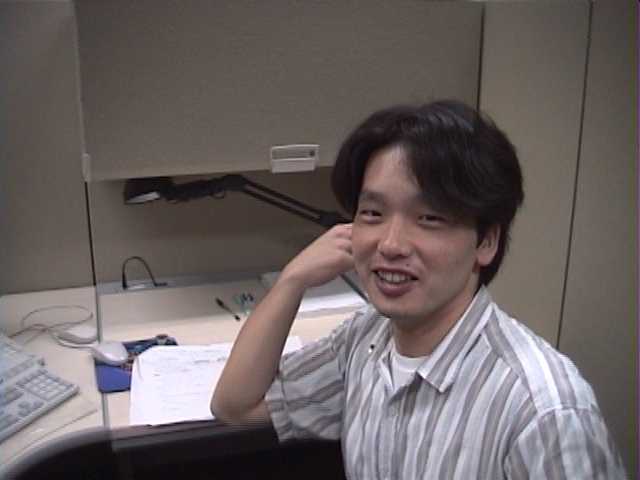
|
非同期型コミュニケーションを支援するインターネットプラットフォームの構築 インターネットにおける非同期型コミュニケーションとして、電子 メールの送受信やWorld Wide Web(以下、WWWとする)による電子文書を介し た情報の伝達のことを考えています。 これらの非同期型コミュニケーションの特徴は、電話による同期型のコミュニ ケーションと比較すると、明白になります。 「相手への配慮」、「保存性」、「再利用性」は、非同期型の利点です。しか し、非同期型では、情報を伝達するために文章を書かなければならず、このこ とは情報の送信者に負担をかけます。また、質疑応答がその場でできないとい うことは、情報の受信者に負担をかけます。
私は、非同期型コミュニケーションを支援するシステムを構築し、上記の負担 を軽減したいと考えています。 中村 勝明と申します、以上。 |
| 李 健 li@jaist.ac.jp 
|
個人情報によってフィルタリングする連想方式情報検索ツールの開発 この研究は、キーワードの関連づけに基づく情報検索(連想方式情報検索)システ ムの利点とユーザの個人情報に着目し、情報検索における再現率と適合率両方を改善 できる検索システムの実現を目指すものです。 ここでは、キーワード検索おける検索する対象(キーワード)の不適切問題や検索 される対象(文書、インデックスなど)の漠然問題などを柔軟に解決できる連想方式 情報検索システムに、フィルタリングとしてユーザが端末側での入力や、作成した文 章やネットワークデータの取り扱いなどに基づいて抽出した個人情報を実装する可能 性および実用性を検討します。 このような工夫をしたシステムの実例として、企業の技術ニーズと、大学および国 立試験研究機関などの技術シーズとを関連付けることで、企業のニーズに適合する シーズの情報検索、あるいはシーズを企業へ展開する受け皿となるニーズの情報検索 の方式をインターネット上のWebサーバを利用してシステム化する方法を検討しま す。 研究では、今までの連想式情報検索にとどまらず、ユーザ情報を検索することで獲得 した個性化情報を連想式情報検索システムに取り込むことで、より柔軟なキーワード による検索システムを開発します。 JAISTにおける教育方針に合わせて、私はただ単に熟練的技術者になるということで はなく、高度な専門知識を持つ「戦略的人材」になることを目指しています。21世紀 は社会構造と経営理念が大きく変わる時代になります。従って、Technologyの最前線 からManagement問題を思考し、そしてManagementの立場からTechnologyの方向を把握 できる人材は、厳しい競争の中でいつもリーダーシープを取る企業にはもっとも重要 な財産になると思います。 他の大学と異なる教育システムと最先端の研究設備の導入、そして大自然に恵まれた 静かな研究環境などは、JAISTの最も大きいな魅力だと思います。しかし、21世紀の 知識社会の構成を考えれば、JAISTにおける異質の交流(文化、思想、価値観と技術 などの交流を含む)がまだまだ不十分だと言えるでしょうか。今の時代では、トップ レベルの研究成果とのコミュニケーションのグローバル化が一流の大学を支える柱で すが、そのうち、コミュニケーションのグローバル化は一番重要ではないでしょう か。 中国北京から来た留学生です。 1984年南京大学理学部を卒業して、6年間半ぐらい北京で働いた後来日しました。 私は大学時代からJAISTに入るまで自然科学、経営学と工学三分野に渡って研究して 来ましたが、「後コンピュータネットワーク時代」にはどんな技術が主流となるかと いう考えに基づき、JAISTの知識研究科を選んで以前と異なる人工知能技術に着目し てきました。従って、私は修士研究のテーマとして、上記のように決めています。 |
| 近藤 真己 mkondo@jaist.ac.jp 
|
| 金子 修三 skaneko@jaist.ac.jp 
|
広島生まれの広島育ちです。もちろんカープのファンです。大学では情報工 学を専攻していました。しかし実際研究室では制御工学をやっていたので特別コ ンピュータにはくわしくありません。趣味はスポーツ全般(特に球技)です。ス キーも大好きで、去年は10回ぐらい行きました。まだこっちに来て冬を経験してな いのでどのくらい雪が降るのかわからないのですが冬になるのがとても楽しみで す。 |
| 窪 智紀 tkubo@jaist.ac.jp 
|
私の研究テーマはグループウェアについてです。 長期間にわたってモチベーションを維持できるような、グループウェアシステムの開発という漠然とした構想を頭に描いています。 この構想でグループウェア部分でのキーとなるのは、インターフェースや、流通する情報へのフィルタリングにあると予測していますが、それらへのアプローチについてまだ模索している段階です。 またグループウェアを使用する組織自体の管理システムにも興味を持っています。 グループウェアという研究テーマは、全体としては漠然としていますし、細部だけを区切って見ると開発の面白さがなくなってしまいます。 現段階では、研究テーマをどの方向にどの程度絞り込むかが大きな課題です。 1976年8月24日鹿児島県にて産まれる。 幼年期から少年期にかけて、関西圏を転々としながら育つ。 舞鶴高等工業専門学校電気工学科卒業後、信州大学経済学部経済学科に編入学。 大学卒業後、理系的知識と文系的知識の融合を目指して、北陸先端科学技術大学院大学知識科学研究科に入学する。 趣味:読書、映画鑑賞、ギターを弾くこと 好きなもの:面白い小説、美味しい料理、心地よい睡眠、小旅行、カレー 嫌いなもの:痛いことや苦しいこと、蛾など虫全般、治療の下手な歯医者、よくしゃべる床屋 |
| 斎藤 主税 csaitou@jaist.ac.jp 
|
グループウェア・マネジメントの研究 最近、米国では組織の知を活用支援するナレッジマネジメントがもてはやされてい る。市場規模としては2000年の米国市場は25億ドル規模に成長する見通しである。知 識の創造がビジネスとして成立しつつある証拠だが、グループウェアソフトの域を出 ていないのが現状である。知識創造の理論発祥の地である日本から、知識創造の本質 を捉えたグループウェア・マネジメントの研究を通して、新しいビジネス及び社会 サービスを模索し、将来的にはビジネスとしたい。研究は特に集団的創造思考の環境 の設定と、そのマネジメントによる集団の創造支援を研究とする。 外注、工程管理のコンサルタントの仕事は、常に企業内のコストに目を配っていな ければならない。如何にコストを押さえるかを担当者と議論する毎日であり、その反 動から知識創造論に惹かれて、JAISTまでやってきてしまいました。 もともと学部では、知的所有権と冷戦後の世界秩序をからめて、知と正義の配分を研 究テーマにしており、知については多少の理解はありましたが、知識創造とは何か、 及びプログラミング言語については、悪戦苦闘中の毎日であります。 |
| 篠田 孝祐 kshinoda@jaist.ac.jp 
|
・ spatial-temporal Database を用いた RealTime MaltiAgent Simulationでの戦略知識の獲得 ・ 階層的組織構造における戦略決定と組織的学習に関する研究 (RoboCup で用いられているマルチエージェントサッカーゲームへの実装) 現在のエージェントシステムでは,人と計算機・エージェント間でのコミュニケーションは研究がすすんでいるが,エージェント間では人の理解しがたい独自のプロトコルが用いられたりするために人がエージェントの意思や行動の理由を実時間上で把握することは難しいといえる.現状ではエージェントの行動の評価などは返された結果をもとに行うしかありません.そこで,エージェントシステムの評価および人との直接的なインタラクションを実現出来るシステムの構築がわたしのなかでの大きな目標です. わたしは,始め人工生命の『創発』という現象に感心し,マルチエージェントシステムに触れながら TempolralDatabase など実時間性にこだわって大学にて学業を学びました.結果,再び計算機にとって『創発』とは何であるかという疑問にあたり.まだ研究らきしものを初めて1年ですが今後も何度となく立ち返るような気がします. 現在は,RoboCup とうい国際的ランドマークプロジェクトで行なわれている研究会議を中心に活動及び研究を進めていますが,この大学院にいる間に人を含めた計算機環境,計算機にとって必要な知識とは何であるのかを考えながら,人と共に生きてゆける計算機の姿を探していきたいと考えております |
| 篠原 明日美 ashino@jaist.ac.jp 
|
性格や個性といったことに興味を持っています. 明示的にシステムに与えられるユーザーの嗜好に関する情報 だけでなく、システムが自律的にそれらの特徴をとり込み、ユ ーザーに適切な環境を提供できるようなシステムを考えたいと 思っています. 篠原明日美(Shinohara Asumi)といいます.田舎にいたとき は気付きませんでしたが、あまりない名前のようです.電話で言 うときは2,3回聞きなおされた後、大概‘あけみ’か‘あずみ’ になってしまいます.一度でわかってくれるとちょっと感動します. |
| 中山 賢二 knakaya@jaist.ac.jp 
|
遠隔教育における教材設計支援ツールの研究 近年、WWWを利用した遠隔教育に関する研究が盛んに行われている。 しかし、実際にWeb上で配信されている教材には、単なるテキストデータ だけのものや、設問があっても解答は択一式であるなど、教材として 十分に役割を果たしていないと思われるものが多い。その理由として、 教材を作成する教員側も、計算機の扱いに習熟していないことがあるため と考えられる。もちろん、市販のWebページ作成ツールなどを利用すれば 容易にページを作ることはできるが、学習の流れに合わせた階層化や インタラクティブな教材の作成という点においては全く力不足である。 この研究では、教材の階層構造を視覚的に表し、尚且つその追加・編集が 容易に行えることで、教員のもつ専門的な教育のノウハウを教材に反映させる ことのできるツールの構築を目標としている。 いわゆる「情報外理系」出身としては、講義はかなりキツいです。 計算機等の環境も噂通りすごいもので、何だかもったいないくらい。 良い意味でも悪い意味でも、「とんでもないところに来てしまった」というのが 正直な感想です。 |
| 永山 覚 snagaya@jaist.ac.jp 
|
教育における発想支援システムの構築 現時点で、考えている研究テーマは、「教育における発想支援システムの構築」についてです。 情報教育が進む中、教師側の問題、設備の導入・管理の問題、授業への活用方法など様々な問題が問われています。それぞれの問題に対しては、各問題ごとに、調査・研究されています。そこで、それを追うような研究ではなく今までにない新しい視点で、子ども達の考えを支援していくようなものを作りたいと考えています。それは、今までの授業の形体を根本的に変えるようなものではなく、今までの授業+αとして役立つようなものを考えています。 このシステムは、教育の分野だけに利用するだけでなく、それを応用して、様々な分野への利用も可能なシステムにしたいと思います。しかし、最初の目標としては、教育の分野ということに限って行いたいと考えています。 学部時代には、情報教育という宙ぶらりんな学科に所属していました。その為、専門と呼べるような専門が無く、JAISTの授業に悪戦苦闘の毎日です。 やりたいことが沢山あるのに、よく眠ってしまい自分自身が嫌になることがたまにあります。 ここに来て、たった3ヶ月しかたっていないのにもう1年くらい経っているような気がします。とても不思議な錯覚に陥っている今日この頃です。 |
| 尾澤 重知 s-ozawa@jaist.ac.jp 
|
高等教育におけるデジタルメディアを利用した学習支援に興味を 持っています。根元的には「支援」とはなんぞや、というメタな問 いを持ちながら、「支援」の功罪両面を明らかにしていきたいと考 えています。 具体的には、「問題発見」や「問題解決」型の非構成的・非系統 的な学習環境のあり方、あるいは日常的な営みに着目しています。 その中で、学習者の内省的思考(reflection)に足場をかけたり (scaffolding)、学習者間のコミュニケーション(共同学習) の促進を目的としながら、自己形成の一助になるようなメディア利用 のあり方を考えていきたいです。 高等教育にこだわるつもりはないのですが、スペシャリストとジェ ネラリストのバランスとか、理系と文系という「二つの文化」が存在 している現状に疑問を持っていた、というのが根底にあります。学習 者中心の研究のスタンスは今後も重視したいところです。 東京生まれの宮城県育ち。学部時代は、様々なプロジェクトや研 究会等に「参加」することで、実に多様なことを学んできました (少なくても本人はそう思っている)。その中で経験的なもの、理論 的なもの、実践的なもののバランスや関係の取り方が、一つ悩みで した。知識科学研究科に入ったのも、上のような問題意識があったか らです。既存の枠組みとしては、社会心理や認知心理に関心があり、 観察とか、フィールドワークが好きなタイプです。 趣味:読書(でも最近時間がない)、温泉に入りたいなぁと思うこと。 |