文部科学省マテリアル先端リサーチインフラ(ARIM)シンポジウムを本学で開催
9月11日(木)、9月12日(金)の2日間、本学にて、「ナノ物性の可視化と理解:AIと拓くマテリアル解析の新展開」シンポジウムを開催しました。文部科学省マテリアル先端リサーチインフラ(ARIM)事業の一環として開催された本シンポジウムには、オンラインと現地合わせて150名を超える参加者が集まり、活発な議論と情報交換が行われました。
今回のシンポジウムでは、電子顕微鏡(TEM)像や分光データを活用したAIによるマテリアル解析の新たな展開をテーマに、最前線で活躍する研究者が講演を行いました。ARIM事業では、TEM画像や分光データの収集・蓄積を進めており、今後のデータ公開・共用に向けた準備が進んでいます。
【プログラム概要】
1日目(9月11日)
初日は、本学先端科学技術研究科副研究科長・大島義文教授の挨拶に続き、以下の招待講演が行われました。
①武藤俊介 教授(名古屋大学)
TEM応用における計測インフォマティクスのビジョンと課題について講演
②志賀元紀 教授(東北大学)
微細構造計測データに対する機械学習の応用について紹介
③溝口照康 教授(東京大学)
生成AIを活用した計測データからの情報抽出と物質設計について講演
④木本浩司 センター長(物質・材料研究機構(NIMS))
4D-STEMと教師なし機械学習によるナノ領域構造解析について発表
2日目(9月12日)
⑤ダム ヒョウ チ 教授(本学共創インテリジェンス研究領域)
Data-Driven AIによる材料動態の可視化について講演
⑥井原史朗 助教(九州大学)
情報科学を援用したナノスケール幾何学情報の抽出と3次元可視化について紹介
⑦麻生浩平 講師(本学ナノマテリアル・デバイス研究領域)
画像処理を活用した電子顕微鏡画像からのナノ材料情報の抽出について発表
閉会にあたり、本学ナノマテリアル・デバイス研究領域 高村由起子教授(ARIM業務責任者)が総括と今後の展望を述べ、盛況のうちに終了しました。
終了後、参加者からは、「生成AIの知見が研究に活用できそうだと感じた」、「結晶粒界の可視化が非常に興味深かった」、「実験家の視点に近い取り組みが印象的だった」などの感想が寄せられました。
今回のシンポジウムは、TEMデータを活用したデータ駆動型研究の可能性を広く共有する貴重な機会となりました。本学は今後もARIM事業を通じて、マテリアル解析の新展開を支援していきます。

開会の挨拶をする
大島義文教授

①武藤俊介教授
(名古屋大学)

②志賀元紀教授
(東北大学)

③溝口照康教授
(東京大学)

④木本浩司センター長
(NIMS)
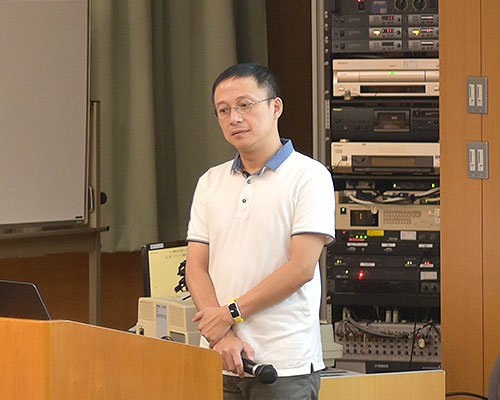
⑤ダムヒョウチ教授
(本学)

⑥井原史朗助教
(九州大学)

⑦麻生浩平講師
(本学)

閉会の挨拶をする
高村由起子教授
令和7年9月29日
