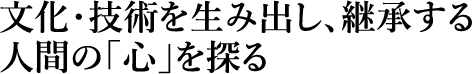中分 遥 准教授
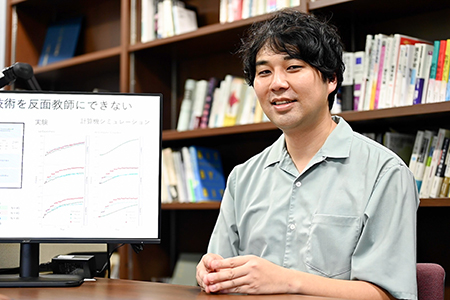
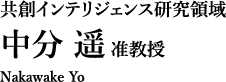
学士(国際教養)(2011年3月 上智大学)
修士(心理学)(2013年3月 上智大学)
博士(文学)(2017年3月 北海道大学)
オックスフォード大学人類学・博物館民族学学部認知人類学ポスドク研究員、九州大学大学院人間環境学府特任助教、高知工科大学経済・マネジメント学群助教、安田女子大学心理学部ビジネス心理学科講師を経て、2024年4月より現職。専門は社会心理学、文化情報学。
科学技術、宗教、物語、芸術などの文化現象は、いずれも“人間”というフィルターを通って継承されます。人間が創る文化は無限ですが、時間の経過とともに特定の方向に変化し、人間に受け入れられないものはやがて失われます。中分准教授は、心理学や文化情報学の手法を中心に、データ分析、シミュレーションなどを駆使して、文化と、文化を生み出し継承する人間の心を追究しています。
文化と人間社会の関係を明らかにする
学部時代は宗教学や文学を学び、大学院では心理学の領域で、実験や数理モデルにより人間の行動を予想する研究に携わりました。その後、オックスフォード大学の人類学・博物館民族学学部でポスドク研究員を務め、フィールド実験や文化資料の分析に従事。帰国後は、数理生物学の研究者らと共に、“石器”という技術を人間がどう進化させてきたのかを探る研究プロジェクトに参画しました。
2024年、JAISTに「人間行動・文化進化論研究室」を開設し、科学技術に加え、宗教や、民話や伝承などの物語も研究の対象としています。
科学技術も宗教も物語も、人間が創り、継承してきた文化であるという点は同じです。私たちの研究室では、人間はどのような文化を創ってきたのか、文化を継承する人間の認知バイアスはどういうものなのか、文化にはどんな構造があるのか――、といったことを心理実験や計算機シミュレーション、文化資料の計量的分析などの手法を通じて明らかにしようとしています。
人は「失敗」から学べるか
具体的な研究テーマの一例として、バーチャル空間で“矢尻”を作製し、“狩り”をするゲームを通じ、人間がどのように他者から技術を学習するかを実験的に検証しています。
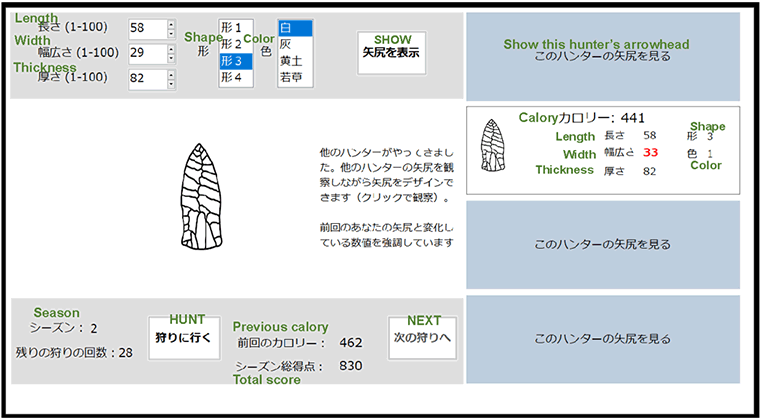
上記の画面ように、ハンター(参加者)は、長さ・幅広さ・厚さ・形・色の5つのパラメータを操作して矢尻を作り、狩りを行ってポイントを獲得します。実験では、ハンターが他者のパラメータを見ながら、より高いポイントを獲得できる矢尻のデザインを探索する過程を観察します。
ここから見えてきたのは、人間は成功している人の情報を見てパフォーマンスを上げることには長けているものの、失敗している人の情報を活用することは苦手だということです。これがAIであれば、学習できるデータが増えることから当然パフォーマンスは上がります。しかし人間が失敗を反面教師にするためには、個人学習に拠るのではなく、組織でパフォーマンスを上げるようなしかけが必要だと考えられます。他にも、チームで矢尻の技術開発をすると、ひとりで取り組むよりパフォーマンスが下がるという興味深い実験結果も出ています。

現代社会で「タタリ伝承」を研究する意義
人間は、科学的な合理性より、不思議なもの、面白いもの、予測できないものに惹かれる傾向があります。シャーマンなど呪術的な力を持つ人物が社会的権威を持つ例は多いですし、妖怪の存在は民間伝承として浸透しています。科学的な知識がなかった時代は、こうした存在が重要な役割を持っていたと考えます。たとえば「この場所の木を伐採してはいけない」というとき、今であれば「土砂災害が起きるから」という合理的な説明ができますが、そうではない時代は、人々は「森の神様のタタリがある」という伝承に従って行動し、災害の発生を防いでいたと予想されます。現在、日本の伝承に関連するデータベースの分析を進めていますが、データ分析の観点からも自然災害とタタリ伝承の関連性が見えてきています。
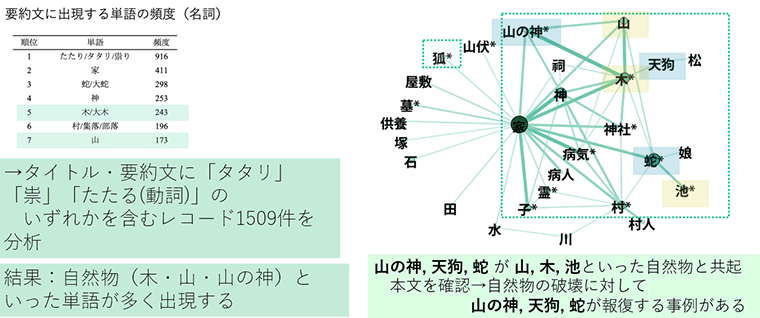
伝承が人間に受け入れられてきたように、現代の人間に対しても、科学的、合理的にものごとを伝えるより、物語形式で伝えるほうが効果的なケースもあるかもしれません。
一方で、反直観的なものに惹かれる人間の心理を利用し、カリスマを装って信者を集めるような組織が生まれる例は少なくありません。こうした問題に対しても、伝承や物語の研究手法が応用できると考えています。
SNSの情報拡散を加速するのは誰?
心理学的なアプローチで、現代的な課題に関連する研究にも取り組んでいます。SNSの情報拡散の分析はそのひとつです。朝日新聞社などとの共同研究で、SNS上のインフルエンサーの影響力について検証を行い、インフルエンサーが「他者の投稿」をリポストすると、その投稿がさらにリポストされる確率が一般ユーザーに比べて高いことを明らかにしました。インフルエンサー本人が作成した投稿だけでなく、インフルエンサーがシェアした他人の投稿でも、拡散力を持つことを示しています。
SNSの言論空間は、想像以上にインフルエンサーの影響で形成されており、私たちの研究成果は、広報戦略や誤情報対策の指針として活用できると考えています。
twitter(現X)におけるインフルエンサーのリポスト影響力
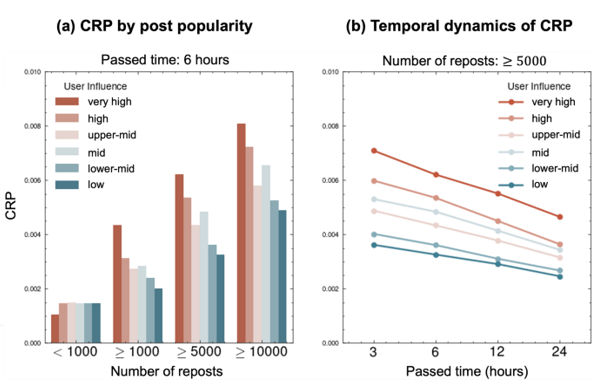
研究を物量勝負にしない
研究活動においては、物量勝負ではなく、新しい視点で切り込むことを重んじています。時間や資源を惜しみなく投入する大規模な研究室とは張り合うのは分が悪いと考えていますし、望ましいとも思いません。誰もが見てみたい結果であるけれども、誰も手をつけてこなかったことに焦点を当て、プロジェクトごとに多様な専門性を持つ研究者と連携します。分野融合は目的ではなく、目的を達成するうえで他分野の知見や技術に頼らざるを得ない局面があり、結果的にそうなるものだと考えています。
「無理なく研究を続ける」を指針に、現状維持に努め、この分野を追究したい学生・研究者の方々が、落ち着いて研究に取り組める拠点でありたいと考えています。
令和7年11月掲載