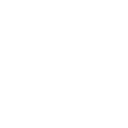はじめに
近年、記憶デバイス内で削除したデータを簡単に復元できるソフトウェアやアプリケーションがフリーで多数存在しています。本学の教育研究等で利用したPCやUSBメモリ等を、記憶デバイスの情報消去を充分に行わずに廃棄・譲渡すると、第3者によって過去に保存されていたデータを容易に復元されてしまう危険性があります。本学で使用したPCや記憶デバイスを廃棄する場合には、下記を参考に1・2のいずれか(または両方)を必ず実施し、情報消去を徹底してください。
1. ソフトウェアによる消去
最近のATA規格のSSD/HDDの多くには「Secure Erase/Enhanced Secure Erase」と呼ばれる、高速かつ安全に情報消去機能があります。Secure EraseについてはPCメーカーからソフトウェアが提供されている場合やPCのBIOSで実行できる場合があります。
例)
- Microsoft Surfaceシリーズ: Microsoft Surface Data Eraser
docs.microsoft.com/ja-jp/surface/microsoft-surface-data-eraser
- Sony VAIOシリーズの一部: BIOSでのSecure Eraseの実行
solutions.vaio.com/3906
2. 物理的な消去・破壊
情報社会基盤研究センター受付にハードディスクを磁気・物理破壊する機材を設置しています。PCを分解しHDDを取り出せる場合には、予めHDDを取り出して本センター窓口にお越しください。なお、ノート型PC・タブレット端末などリチウムイオンバッテリー等を内蔵しているデバイスについては、発火など安全上の懸念がありため、分解は推奨しまでききません。ソフトウェアによる消去を推奨します。
2. 物理的な消去・破壊(COMBO-FBIの使い方)

磁気によるデータ消去と物理破壊を行う複合型HDDクラッシャーです。
操作方法は操作説明書を参照し、操作してください。
※磁気による消去を行いますので、本体近辺には強い磁場が発生します。
クレジットカード情報や本学の教職員証の磁気バーコード部分が破壊され読めなくなる場合もありますので、実施時にはご注意ください。